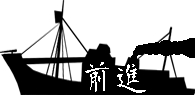お や じ の ア ル バ ム

この謎のバス、京都なの?
おやじメモ
なし

ブログ時代からずっとこのバスを探していました。てっきり横須賀だと思っていたのですが、ひょんな事からこのバスと同じデザインのバスを発見。なんと旧京都交通のバスでした。

ただし年代が違うようでバスの形が違います。
カラーの方には正面の屋根についている三つの緑のランプ「速度表示装置(点灯の順番は、時速40km以下で一つ目助手席側(○○●)、 時速40km超~60km以下で二つ目運転席側(●○●)、 時速60km超で三つ目真ん中(●●●)の順です)」が付いていません。ヘッドランプは二灯式から四灯式に変更されています。きっと道交法の改正とマイナーチェンジによるものでしょう。
日本のバス
明治36年(1903年)までは、全国的に乗合馬車だった。
同年3月に大阪で開かれた内国勧業博覧会への旅客輸送のために、梅田と天王寺を結ぶ臨時バス路線が開設された。これが日本初のバスかと思いきや、日本バス協会によると、同年に二井商会が京都市内でのバス営業運転を始めようと試みた9月20日をバスの日と定めている(昭和62年)。ところが何故か、初日から営業中止勧告を受け、実際に正式営業が始まったのは11月21日だったという。
また、使用車両は6人乗り(運転手、助手、乗客4名)であったため、車両的にバスと言えるのか議論が残っている。
明治38年(1905年)2月、広島の横川から可部の間に12人乗りのバス(写真)が運行された。これを日本で最初のバスの運行とする説もある。個人的にはこちらの方がバスに見えるのですが、残念なことに車両の故障などが頻発し、費用の不足(部品の調達のため銀貨を溶かした事もあった)もあったため、9月で営業を終了した。
どの業界でも草創期は大変ですよね。バスにとっては道路が舗装されてないことから高速で走れず故障が多い。それまで輸送を担っていた人力車や馬車運営者から敵視され妨害を受け、法整備も進んでいない時代だった。なかなか大変だった様ですが、逆に自動車さえあれば個人で営業できたとも言われています。


昭和8年(1933年)、自動車交通事業法が整備され、一路線一事業者の原則が作られた。これにより各社の統合が始まったが、戦争が始まるとバス事業を一旦全面休止する。
戦後は燃料の確保が難しく、昭和24年ごろまでは、木炭や薪などの代用燃料車への転換を余儀なくされた。
ようやく国産ディーゼルエンジンのボネットバスが走るようになり、大型化が進む。
昭和28年(1953年)、しばらくボンネットバスが主流だったが、日野自動車が国産
初のセンターアンダフロアエンジン・バス(ミッドシップ)を販売する。日野はこの
BD系バスにブルーリボンバスと命名し、昭和36年まで製造している。


おやじが撮った写真の撮影場所まではわかりませんが、車種は日野自動車のBD系、バス会社は旧京都交通のバスです。撮影時期は昭和32年前後だと思われます。
丁度その頃、弘前駅前にはまだ馬車がいました。昭和34年生まれの私の記憶では、30年代後半まであったと思います。弘前駅前から上土手町あたりまで乗車した記憶があります。
そして馬車には、
アポロ式方向指示
器が付いていたの
を覚えています。



段落です。テキストを追加したり編集するにはここをクリックしてください。ここはお話をしたりあなたについて訪問者に知ってもらうのに絶好の場所です。
2017年5月15日の弘前駅です。
東京タワー完成まで、あと1年(昭和33年12月23日)。
青函トンネル開通まで、あと31年(昭和63年3月13日)。
東北新幹線の八戸駅開業まで、あと45年(平成14年12月1日)。
東北新幹線の新青森駅開業まで、あと53年(平成22年12月4日)。
東京スカイツリー完成まで、あと55年(平成24年5月)。
北海道新幹線新函館北斗駅開業まで、あと59年(平成28年3月26日)

この建物は全くわかりません

長浦港に16Tがいた
マースクの貨物船
日本とデンマーク