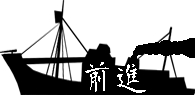お や じ の ア ル バ ム

入港祝い

←タラップ
おやじメモ
帰港
ついに長浦港入港ですね。大発でどんどん人が乗り込んで来ます。私もこうして母船に乗り込んだ記憶があります。タラップを登る背中がワクワクしていそうですね。

子供心にこのタラップが恐かった事をぼんやり覚えています。何しろ足元から海面が見えるし、この写真では分かりにくい高さがあります。
左下の写真は同船(二代目日新丸)がタラップを収納ぜずに航行している場面ですが、喫水線が高いので、おそらく完成後のテスト航行時に撮影された写真かもしれません。
いよいよ甲板で、製油課が三日かけて下拵えしてきた焼き鳥風鯨肉が炭火の上にあげられ、お酒が振舞われるのですね。
でも、まだ使える埠頭はないようです。
二代目 日新丸

おやじメモ
入港祝い この日 女優の久我よし子 湯の町エレジーを歌った歌手と楽団の人達が舞台に立つ。
舞台を造って演芸を行う 笛を吹けと事業長兼副船団長から命ぜられマイクの前に立つ自分
挨拶は中尾事業長 赤城の子守唄 踊りは宮城県の二人
久我よし子さんといえば、同期に三船敏
郎、堀雄二、伊豆肇、若山セツ子、堺左
千夫らをもつ女優さんで、本名小野田 美子(おのだ はるこ)。昭和22年(1947年)、学習院を中退し、『四つの恋の物語』で映画デビューを果たす。
この写真が撮られたであろう昭和29年には、3月16日に映画「女の園」が公開された
ばかりでした。
原作:阿部知二『人工庭園』
監督:木下惠介。
製作・配給は松竹
湯の町エレジーは、1948年(昭和23年)に近江俊郎がヒットさせた曲です。
作詞:野村俊夫、作曲:古賀政男。ギターの音色を特徴とする「古賀メロディー」を代表する曲であり、同時に近江俊郎の代表曲ともなり、彼の人気を不動のものにした曲となりました。しかし、玉置宏によると、当初は霧島昇が歌うのを想定して作られた曲であるとの事。発売当時、40万枚という、当時としては驚異的なレコード売上枚数を記録した。
さらに本曲をモチーフとして、1949年(昭和29年)5月に東宝が『湯の町悲歌(エレジー)』を近江俊郎の主演で製作・公開された。
こうして調べてみると「なんだ映画の宣伝か」とも思えるが、当時の日本のスター達が日新丸の入港祝いに華を飾っていたのも時代の1ページですね。
そんなステージの上で横笛を吹いていたおやじ、家でもよく練習していました。
赤城の子守唄とは、作詞:佐藤惣之助、作曲:竹岡信幸、昭和9(1934) 年2月に日本ポリドール蓄音器株式会社により発表された歌謡曲の題名。東海林太郎が歌った。
この曲は、幕末の侠客国定忠治を主題とした松竹制作の時代劇映画『浅太郎赤城の唄』(高田浩吉主演)の主題歌として作られた。哀愁ある旋律と歌詞は大ヒットし、東海林太郎の出世作となった。曲の人気さは物すごく、松竹も映画のタイトルを『赤城の子守唄』に変えた途端、大入りになったほどである。
女の園
湯の町エレジー

赤城の子守唄

おやじメモ
弘前組のネブタと駒踊りの姿
弘前組のネブタと書いていますが、まさかねぶた本体を日新丸に持ち込んではいないでしょう。たぶん、弘前ねぷたの「もんどりこ(凱旋囃子)」か、青森ネブタのように跳ねたのでしょうね。これなら太鼓と笛が有れば出来ますし、手振り鉦はステンレスの灰皿二枚有れば自作できます。みんなで楽しんだのではないでしょうか。
写真の中の左から後ろの三人が、いわゆるネブタの定番衣装です。
南部駒踊り
馬と関わりを持つ祭りは全国的にありますが、南部駒踊りは、旧南部領(青森県南太平洋側と岩手県北)にだけ伝わっている独特の形が特長です。
八戸組が踊ったと書いてあれば確定なんですが、弘前組(津軽衆)が南部駒踊りを踊ったとは考えにくいですよね。
やはりそこは幼い頃から慣れ親しんでいる南部衆が踊っていたはずです。
駒踊りが定型化したのは元禄年間(1688~1703)または享保年間(1716~1735)とされ、以来約300年の歴史を持ちます。伝承は各地にあったものの、現在は南部の馬産地といわれる石沢(三戸郡倉石村)、洞内(十和田市)、高館(八戸市)、浜三沢(三沢市)、赤保内(三戸郡階上村)の5つの保存会にまとめられ、青森県の無形文化財に指定されています。
戦後間もない捕鯨船団はどの会社の船団も、乗組員の殆どが元軍人だったでしょう。戦争を知らない最初の世代であるおやじ達は、いやいや、戦地に行ってな
いだけで戦争は体験してますよね。そんな集団の中で若者達は鍛えられ、誇りを胸に大きな仕事をしていたのかもしれません。きっとそんな捕鯨人達にとっては、郷土の祭りこそ南氷洋での疲れを取り、再び血肉を沸騰させるような元気が湧き出てくるものではなかったか。
鎌倉見物
二代目日新丸 入港式準備完了