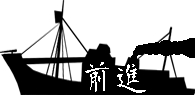お や じ の ア ル バ ム

天洋丸 と 幡州丸
おやじメモより
粛の海
左奥が紛れもなく第三天洋丸です。白線なしです。
前ページのおやじメモから右手前が幡州丸だろうと思われますが、確定できません。なにしろ播州丸は沢山あって、戦時中は初代日新丸や初代第二日新丸のように米軍の魚雷の餌食になっています。
「大洋漁業株式会社 Taiyo Gyogyo K. K.」 というページに、以前調べた時はデータしか載っていなかったので、てっきり昭和29年に建造されたばかりの第二播州丸かと思っていまし
たが、今回の確認ではデー
タがさらに詳しくなり、写
真も掲載されておりまし
た。この船をよく見ると違
うことが判明。
まず、形が違います。当然ですが船首に書かれている船名が「第二播州丸」と五文字です。

第二播州丸
71801/JEOI 冷凍/冷蔵運搬船 1,246G/T 1,535D/W
起工 1954.2.10(昭29) 進水 1954.3.26(昭29) 竣工 1954.5.10(昭29)
Lpp 70.00 B 10.80 D 5.50 m 主機 D 新潟鉄工 1,200PS 1基 10.8/13.5kt
川崎重工業株式会社(神戸)建造 Sno.934 大洋漁業株式会社(東京)
第二播州丸 Banshu Maru No.2 冷凍運搬船

それに対して、おやじが撮った右手前の船は三文字。はて、播州丸なのか?
ん〜、播州丸か? 初代なら第一と書かない場合がありますよね。
ちなみに播州丸は
明治38年10月に日本初の西洋式木造鮮魚運搬汽船(発動機船)である第一新生丸を誕生させた中部幾次郎(大正13年林兼商店を創立)が、明治40年に、朝鮮に進出して成功を収める。それをきっかけに新生丸を増やし、大正14年には第四十八新生丸となっていた。
中部氏は大正5年から直営漁船を始め、第一魚生丸の鯖巾着網を主として15隻建造し、朝鮮近海を主に台湾付近まで魚場を拡大している。
トロール漁船は朝鮮の方漁津を母港とし、運送船の播州丸と第二播州丸は暇な時に運用されていたが、事業が大きくなると、鋼船の冷蔵・冷凍室を備えた播州丸シリーズも増え、大正11年には第17播州丸となっていた。このころから播州丸は冷凍運搬船だったようですね。
そして戦争が始まると他の船舶同様、お国のために働かされることになる。
大日本帝國海軍 特設艦船で発見できた中で一番大きな数字をつけた播州丸は、特設掃海艇として沈没した「第五十六播州丸」です。おそらく56隻以上あったのでしょう。ただし、林兼商店が他社の船舶を購入して船名を播州丸シリーズに変えている場合もあるので、全て林兼商店が建造したものではありません。
昭和11年(1936年)に大洋捕鯨株式会社を設立し南氷洋捕鯨に初出漁。
昭和18年(1943年)には戦時下の水産統制令により、内地水産部門と大洋捕鯨株式会社等を合併し、西太平洋漁
業統制株式会社に改称。戦局悪化と共に漁業用船舶を徴用されて大打撃を受けた。
昭和20年(1945年)戦後、大洋漁業(株)に社名変更。中部幾次郎は敗戦後、日本の食糧難を解決するために
と、早急に捕鯨再開をGHQに進言する。
昭和21年(1946年)5月19日、中部幾次郎は大洋漁業の第一日新丸船団が長崎から南氷洋へ出向する姿を見ぬま
ま、他界した。
11月17日、大洋漁業の第一日新丸が、天洋丸のほか冷凍運搬船1隻、キャッチャーボート5隻
と船団を組み、戦後における捕鯨再開の第一陣として、長崎港から一路南氷洋へと出港。

進水年 建造所 船名 総トン数
1900年(明33) 三菱造船所 第六播州丸 Banshu Maru No.6 643
1923年(大12) 神戸製鋼播磨 第二十二播州丸 Banshu Maru No.22 142
〃 〃 第二十五播州丸 Banshu Maru No.25 142
1945年(昭20) 林兼造船 第三十六播州丸 Banshu Maru No.36 998
1946年(昭21) 林兼造船 第三十八播州丸 Banshu Maru No.38 998
1954年(昭29) 川崎重工 第二播州丸 Banshu Maru No.2 1,247
おやじの写真から推測すると、捕鯨船よりやや大きめのこの船はまだ表にはない播州丸かもしれません。昭和29年に建造された第二播州丸の先輩ではないかと思われます。それなら三文字でも納得なのですが、どうでしょう。
戦後、大洋漁業が所有していたと思われる播州丸を「大洋漁業株式会社 Taiyo Gyogyo K. K.」から拾うと下記表の通りです。
第三十二播州丸が第一次南氷洋捕鯨から東京港へ入港。昭和22年の動画です
昭和22年の南氷洋鯨肉配給では。
一人当り三十匁 二円二拾五銭とあります。

「匁(もんめ)」とは日本の尺貫法です。
1891年(明治24年)の度量衡法により、正確に3.75グラムと規定されました。これは穴あき五円玉と同じです。
価格 百匁=375g 7円五拾銭
一人当り三十匁=112.5g 二円二拾五銭
お腹いっぱいになる量ではありませんね。
日新丸と天洋丸のローグサイド
鯨肉を中積船へ