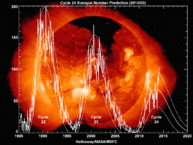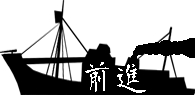お や じ の ア ル バ ム

砕け散る氷 オーロラ
おやじメモより
砕け散る氷 朝か夕方か?一月から二月中旬まではハッキリしない
オーロラが空一杯に現れ流れる 赤、青、黄、緑
南極圏の内側からオーロラを観ていたようですね。それにしてもこの氷山は、アイスピックで砕いているような形をしています。しばらく雪が降ってないのだろうか。
因みに南極大陸での平均気温は1月 −25.9℃、2月 −38.1℃です。
残念ながら白黒写真なので色は確認できませんが、伝えたかったのでしょう「赤、青、黄、緑」と記録されてます。
では、今見れる方法で確認してみましょう。
オーロラの発生

小学校の理科の時間で方位磁石を使った経験があると思います。赤がN極で白 (または青) がS極で、赤のN極が北を指すと習いますよね。
それは地球が大きな磁石で、北がS極で南がN極だからです。えっ?逆でしょう?と思った方も多いと思いますが、磁石は「SとN」は引き合いますが「NとN」「SとS」は反発するのです。

日常では北をNorth、南をSouth といいますし、通常それで困る事はないので気にする事もないのですが、地理上の「NとS」は、磁気圏の話になると逆になります。
さらに地理上の北極点と磁場上の地磁気北極はズレています(地磁気南極も同じ)。地球の自転軸に対して約 10.2 度(2006年)傾いていて、しかもゆっくり移動しています。
← 左図の磁力線には太陽風 (太陽から吹き出す極めて高温で電離した粒子(プラズマ))が考慮せれていません。
↑ 上図の磁力線に、左から太陽風を吹きかけると右図になります。
太陽風の勢いを受けて地球の太陽側(昼側)の磁気圏界面の位置は地球半径の10倍程度 (高度約60000km)まで押されています。 ただし、この位置は太陽風の強弱で大きく変化します。
太陽と反対側(夜側)の方向には、地球半径の200倍以上にまで伸びていることが確認されており、長く引き延ばされた部分を磁気圏尾といいます。

川の流れ
渓流釣りなどで川の流れを見ていると、大きな石があるところでは石の川上側で水があふれ、川下側では流れが止まっていたり、場合によっては水が逆流していることがありますよね。また、大きな川に架かっている橋脚の川下側にも見られる事があります。それと同じ事が宇宙でも起こっていると考えると、解りやすいかもしれません。

プラズマ
太陽フレア(太陽面爆発)やコロナホールから放出されるプラズマの威力は水素爆弾10万~1億個と同等であるという。通常100万度のコロナプラズマは数千万度にまで加熱されます。また、多量の非熱的粒子が加速され、衝撃波やプラズマ噴出が発生し、時おりそれらは地球に接近して、突然の磁気嵐を起こします。
プラズマは電子を手放した原子(プラスの電荷)と、自由になった電子(マイナスの電荷)の集まりで、高エネルギー状態になっています。
原子
すべての物質は原子でできています。原子は原子核とそのまわりを回転している電子で構成されています。原子同士が窮屈な個体、少しゆるい関係の液体、自由に飛びまわれる気体、そして宇宙を旅する第四の状態がプラズマです。
原子にエネルギーを加えると固体→液体→気体と順にエネルギーが高まり温度が上昇し、動くスピードが増します。さらにエネルギーを加えると原子を構成している電子が原子の束縛を振り切って自由に動き回ることができるようになり、プラスの電荷をもったイオンとマイナス の電荷をもった電子に別れます。この状態をプラズマといいます。

化学1章3話「原子のつくり」byWEB玉塾
@mic GO! GO!
~原子と原子核 基礎講座~ (1)陰極線
@mic GO! GO!
~原子と原子核 基礎講座~ (5)原子の構造
大きさ
原子の大きさは約100億分の1m。そうは言われましても実感ゼロですよね。
原子の中身は電子が動けるようにスカスカのようです。その中心にある原子核を400兆倍して卓球玉の40mmにした時、原子の大きさはおよそ40kmになります。小さな原子核(卓球玉)は原子全体の99.9%以上の重さを持っています。原子核の周りを飛び回っている電子の場合は、大きさがないといえるほど小さく、今のところ単体でこれ以上小さいものはありません。
NASA 太陽フレア
密度
1cm2あたり5個程度の密度で
移動しているようですが、磁場の
影響を受けて変化します。
太陽風の温度
太陽の表面で約100万度。地球付近では約10万度のプラズマ粒子となるガスです。
地球磁場
巨大な磁石でもある地球が作り出している磁場が、太陽風から地球を守っています。
太陽から吹き出したプラズマの一部が、約1億5000万 km 先の地球へ向かって秒速450kmの速さで飛び続けたとすると、3.85日後(時速300 kmの新幹線では50年以上)には地球磁場と衝突する孤状衝突波へ到達します。

磁場をまっすぐ飛べないプラズマは磁力線に沿って迂回路を
取るようになり、私共へ10万度のプラズマが直接降り注ぐこと
はありません。但し、一部のプラズマが磁気圏のカスプから入
り込みます。
迂回して通り過ぎたプラズマの一部は、なぜか磁気圏尾から侵入して逆流してきます。(ひょっとすると磁気圏尾で磁力線がクロスするからかもしれません)さらにプラズマはプラズマシートと呼ばれる場所に溜まり、何かを切っ掛けに地球へ向かって加速します。
一度加速したプラズマは磁力線にそって速度を上げ、地球の大気(電離層)へ高速降下します。この時に大気中の粒子と衝突し、衝突された大気粒子が一旦励起状態になったあと、元の状態に戻るときに発光するのがオーロラです。
発光の原理だけならば、オーロラは蛍光灯やネオンサインと同じようです。
右の動画は太陽風として宇宙を旅する元気溌剌な原子と電子達、プラズマの動きを黄色で表現してみました。
太陽風の風速
実際のプラズマ流は秒速300~900km(平均450km)の高速で移動します。
オーロラの高度
下端はほぼ一定の100~105km。上端については約500km~1000kmと観測結果に幅があり、上端へいくほどぼやけます。
また、プラズマは地磁気北極や南極の一点に向かっているのではなく、右図のように、磁力線に沿って円(やや楕円)を描きながらカーテンを作っています。
オーロラが発生している領域を「オーロラオーバル」と呼び、活動が活発になると広がります。昼夜を平均すると地磁気の緯度でおよそ60度から70度のあたりにオーロラがよく発生するので、この領域を「オーロラ帯」(オーロラベルト)という。
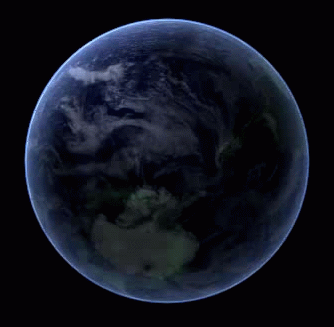
太陽とオーロラ
単純に太陽の活動が活発になると、プラズマの放出が増え、オーロラが見える。ということになりますよね。
太陽風は、太陽にコロナがある限り吹く風なので、平時でもある程度は観察できるようです。
では、いつ強くなるのか?
太陽風が強くなる三つの現象は
1、太陽フレアの発生。
2、突発的なコロナ質量放出により放出されたコロナの地球磁気圏への衝突。
3、高速の太陽風が噴出するコロナホールの生成。
☆コロナホールは数か月間、ほとんど同じ場所で継続するため、太陽の自転周
期(およそ27日)を計算するだけでオーロラの活動を予測することができま
す。またコロナホールは太陽活動周期である11年に影響を受けながら、黒点
数がピークになった年から数年後に増加します。
よって、旅行会社は黒点周期の11年ごとに「オーロラの当たり年」「オーロラ最盛期」キャンペーンを
張り、オーロラツアーを組んで集客します。
太陽がプラズマを大量放出すると、旅行会社が儲かることになりますね。しかし、喜んでばかりはいられません。NASAの発表によると「2012年7月23日に地球の軌道上を駆け抜けた太陽風は、過去150年間で最も強力なものだった。もし、(この太陽風の)発生がほんの1週間前にずれていたら、地球は集中砲火を浴びていただろう。現代文明を18世紀に後退させる威力があった」と。
オーロラと日本
日本語では、オーロラを古来「赤気(せっき)」または「紅気(せっけ)」と呼ばれていました。最古の記述は日本書紀まで遡ります。
620年:推古天皇28年12月30日には、「天に赤気があり、その形は雉の尾に似ていた。長さは一丈(約3.8メート
ル)あまりであった。」という記録が残されています。
1204年:元久元年、藤原定家の明月記でも同年2月21日に「北の空から赤気が迫ってきた。その中に白い箇所が5個
ほどあり、筋も見られる。恐ろしいことだ。」と、オーロラのことだと推定される記録が残されている。
1770年:明和7年9月17日に出現したオーロラは、およそ40種の文献に登場しており、肥前国(長崎県・佐賀県)で
も観測されたという記録が残っている。
明 治:明治期から「赤気」という言葉ではなく、「極光」や「オーロラ」が使われるようになった。
1912年:明治45年、南極探検家の白瀬矗は、3月に南極から帰る際に現れたオーロラをスケッチし、報告書『南極』
に残している。
1934年:昭和9年、日本社会へは同年に開始された南氷洋捕鯨により、オーロラが少しずつ紹介され始めた。
1958年:昭和33年2月11日は天候に恵まれたこともあって、北陸から関東ににかけて赤い、一部では脈動や黄色
も見られるオーロラが出現した。ちょうど国際地球観測年に当たる1957年から気象庁は各地の測候所へ
オーロラ観測を命令していたため、この日は長野県・東北地方・北海道などでも観測された。この日は世
界中で電波障害が起き、ヨーロッパでもオーロラが見られた。
昭和33年2月12日 新潟新報
昨夜赤いオーロラ
北方に県下各地で観測
11日午後7時ごろ北方海上上空に赤く輝く異常現象を強い難しで発見、同じ時刻に新発田、村上方面でも同様異常現象を発見、火事ではないかと、第九管区海上保安本部が巡視船を出す騒ぎとなった。
なおこの極光は新潟地方だけでなく、北海道、東北地方、富山相川など各地で観測されている

オーストラリアで撮影された写真。 日本ほどの低緯度でオーロラが観測される時もこのように山際が赤黒く染まる。

北海道で北の空を染める赤いオーロラを見た住民が山火事と勘違いして消防車が出動した記録があったり、昭和33年の新潟県で第九管区海上保安本部が火事ではないかと巡視船を出す騒ぎになったこともある日本の赤気(オーロラ)は、上の写真を見るとうなずけますね。
南極や北極で観れるオーロラと違い、日本や他の低緯度に現れるオーロラは赤なんですね。おそらくオーロラの上部だけを観ているのでしょう。可視光線の中で波長が長い赤が波の性質で回折しやすい点もあるかもしれませんね。
「赤、青、黄、緑」のオーロラを生で見るには、「オーロラの当たり年」に極地へ行かなければなりませんね。

おまけ 南極大陸
オーロラと云う光りもの
特別編 第十六利丸の事
しらさぎ城 第五福竜丸 俊鶻丸