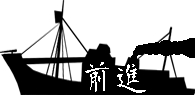お や じ の ア ル バ ム

操業開始! 第六文丸
おやじメモより
早くも船団のトップを争うキャッチャーボートの十五隻は命�中された長須鯨を母船に持って来る
依って製油課の機会はガラガラ運転される
この時代、マルハの日新丸船団では15隻のキャッチャーボートが供戦していたようです。
いよいいよ操業開始!第六文丸はトップクラスだったようですね。
大洋漁業の初代第六文丸は昭和20年7月10日、敗戦直前に新島東方で米海軍に雷撃を受けて沈没しています。どの戦艦から撃たれたかは不明。
昭和17年10月28日に大阪府岬町に開設された 川崎重工 泉州工場だったが、昭和20年7月25日、艦載機50機による空襲を受けてしまう。その後日本が敗戦し、工場使用許可が下りたのは昭和21年12月なのだが、大洋漁業によると写真の第六文丸は昭和21年に 川崎泉州で建造された304tの捕鯨船であることが分かります。
はて? どこに魔法があるのか。
第六文丸のプラモデル
昭和30年代、東京タワーが建った後ぐらいに(株)大洋漁業の捕鯨船「第六文丸」がプラモデルとして販売されていました。時代ですね〜。


・1924年(大正13年)2月 - 富山玩具製作所創設。
・1927年(昭和2年)5月 - 合資会社富山工場を設立。
・1952年(昭和27年)3月 - 富山工場、社名を合資会社三陽玩具
製作所に変更。
・1953年(昭和28年)1月 - 三陽玩具製作所、株式会社に改組
し、三陽工業株式会社に社名変更。
・1959年(昭和34年)3月 - 三陽工業、営業部門を分離独立し、
販売子会社富山商事株式会社を設立。
・1963年(昭和38年)3月 - 三陽工業をトミー工業株式会社に、
富山商事を株式会社トミー(旧トミー)に社名変更。
・1989年(平成元年)3月 - トミー工業、旧トミーを吸収合併
し、社名を株式会社トミーに変更。
・1997年(平成9年)9月 - トミー、株式店頭公開。
・1999年(平成11年)3月 - トミー、東証第二部上場。
・2000年(平成12年)3月 - トミー、東証第一部上場。
・2005年(平成17年)5月13日 - トミーとタカラが合併すること
で合意。
敗戦間もない頃は動くエンジンがないなど、本物の捕鯨船の復興には大変な苦労があったようです。
なんとプラモデルの方はマブチ25が二つ搭載され、単2乾電池2本で走行していたとか。

いつまで見れるかわ�かりませんが、このプラモデルは千葉県南房総市にある「道の駅和田浦WA-O!」に、組み立て前の模型が展示されているようです。(2014年現在)
小学生時代の記憶を遡ると、ほとんどのプラモデルで使われていたモターはマブチ13か丸型のマブチ14だったと思います。マブチ25を2機搭載するということは、プラモデルでも本物の捕鯨船のように破格のパワーを生み出していたのかもしれません。
初代第六利丸
あれこれ調べているうちに、おやじから聞いていた話を活字で見つけました。こちらは初代第六利丸で、次の通りです。
昭和14年3月10日、第三次南氷洋捕鯨で、初代第二日新丸船団のキャッチャーボート「第十一玉丸」「第六利丸」「第八利丸」が氷山と氷原に挟まれて動けなくなりました。
原因は強風から身(捕鯨船)をかわしながら必至に船の舵を握っている時、突如潮の流れと風の向きが変わり、その変化に対応できなくなったためらしい。

残念ながら母船初代第二日新丸も近づけない氷山であり、やむなく捕鯨船の乗組員57名が,氷の上を歩いて脱出することを決断しました。
歩いた距離が3海里だったといいますから、1海里=1.85200kmとすると×3=5.556kmも道無き道の氷上を歩いた事になります。

写真を見る限り吹雪が止んでから出発したようですね。八甲田雪中行軍遭難事件(明治35年)のようにならなくて本当に良かったです。
捕鯨船から持ち出したものは、まずは写真で確認できる竹竿。南極大陸の上を歩くわけではないので、一歩間違えれば冷たい氷の海に身を沈める事になります。竿があれば氷の状態を確認しながら進めるので役に立っていたと思います。運搬に竹梯子も重宝していたでしょう。
そしておにぎりとコンパス。水も持っていたと思います。因みにこう言う場合は、水は水筒の八分目まで入れて歩きながら常に揺らしていると凍りにくいそうです。
こうして捕鯨船を離れた乗組員57名は、母船初代第二日新丸が吐き出す煙や汽笛を頼りに母船目指して氷上行軍を決行し、全員救出されたのです。
残された捕鯨船のうち第八利丸は、昭和14年11月20日に日本水産の第三圖南丸に発見されて初代第二日新丸に引き渡されます。
写真は「大洋漁業80年史」から
参考資料:太平洋戦争時の喪失船舶明細表(汽船主体)
文丸と利丸
巻き上げられる抹香鯨
母船と大氷山