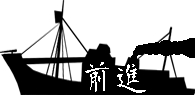top of page
お や じ の ア ル バ ム

日新丸と天洋丸のローグサイド
おやじメモより
天洋丸 肉満量にして鯨油移行し 満船の為に日新丸とローグサイド中

タ
イ
ヤ
右が日新丸で左が天洋丸です。拡大すると日新丸の俎板では鯨を解体中です。
天洋丸は謎の白線入りの第三天洋丸ですね。
大発艇
ボートダビット
白線
ローグサイド中に日新丸から撮った写真ですね。
手前には太いホースが繋がれ、奥ではパイプが繋がれています。波さえなければ大発艇を使うことなく、ローグサイドで鯨肉や鯨油を移せるというわけですね。
鯨油は太い方で行われていたようなので、細いパイプは船の燃料か飲料水かもしれません。
中積油槽船と呼ばれる天洋丸は、いわゆるタンカーの一種であり、鯨油だけでなく原油も運んでいました。
まず、捕鯨船団が使う燃料を積んで日本を出港し、南氷洋の船団に燃料を補給します。空になった天洋丸はそのまま中東へ向かい、中東で燃料を積み込んで船団に戻ります。船団へ補給後、鯨油(商品)を積み込んで欧米へ輸送します。鯨油を売って空になった天洋丸はそのまま中東へ向かい、今度は原油を積んで日本へ戻ります。このサイクルを繰り返していました。
大洋漁業では油槽船を天洋丸のほか、昭和33年に兼洋丸(Kenyo Maru)を建造しています。
化石燃料がまだあまり使えていない時代、それを鯨に求めて乱獲し、アジアまでやって来たのがアメリカ捕鯨ですよね。特に抹香鯨の鯨油は需要が高く、機械油として、照明用として、様々な使われ方をしていました。大型鯨のシロナガスクジラを捕鯨できるようになると、効率の良さからシロナガスクジラの乱獲がはじまり、捕鯨オリンピック時代を迎えます。
やがて油田が発見され、照明はガスや電気に変わり、機械油も代用品が開発されると、鯨を食文化にしていない国は、これで捕鯨をする必要が無くなったという訳です。
捕鯨の歴史と世界史地図
氷山 食糧
天洋丸と播州丸
bottom of page