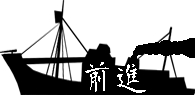お や じ の ア ル バ ム
キャッチャーボート 暴風圏を行く (第十七利丸捕鯨船の事)

暴風圏を突っ走るキャッチャーボートです。
暴風圏とは快晴でも強風が吹いている場所で、大陸が少ない南半球の南緯40°から60°あたりのことです。
「咆える40°、狂う50°、叫ぶ60°」「唸る40°、吠える50°、叫ぶ60°」などといわれてます。
日本から南氷洋へ行くには、どうしても通過しなければならない海域で、キャッチャーボートの場合、スクリューが宙に浮いて空回りするほど船が揺れるそうです。



おやじメモによると
第十七利丸捕鯨船 昭和四十年四月記念 自作品
ネットで探してみたら、第十七利丸 Toshi Maru No.17
総トン数757 進水年不明 建造所林兼造船 とありました。
そして、もう一度暴風圏の写真を御覧になって見て下さい。どんだけ~!ってくらい頭から波に突っ込んでるかがわかると思います。
微かな記憶によると、このモデルは私が小学校入学当時に作ってきたものです。出来映えかなりいいですよ^^
当時、日新丸に乗り込んだ人達の間でブームだったようです。日新丸やキャッチャーボートを作り、お土産にもって帰ったそうですが、残念な事に子供達のおもちゃにされ、池に沈められたりしていたそうです。おやじの場合はイタズラしそうな私からモデルを守る為にケースに入れて背景を描いていじられないようにしてました^^
そのお陰で今も残っている訳ですけどね♪
思い出話を補足
この写真ではよく分りませんが、キャッチャーボートの後ろには上から青・赤・黄のランプが二個ずつ付いています。
おやじとの想い出話では、この三色6つのライトは個体識別に使っていたようです。夜に何色のライトが何個点いているかを確認することで、それぞれのキャッチャーボートがちゃんと安全に側に居るかどうか、互いに目視できるのだそうです。
ところが他のキャッチャーボートの写真を見てもライトを確認できません。この船だけだったのか、時代が違うのか、今のところ不明です。もしかすると一時的な方法だったのかもしれませんね。
(2011年08月18日)
なんと2014年8月、おやじが制作モデルにした第十七利丸のその後が分かりました。
「オトナの絵本(アダルトではありません)」をコンセプトにした「末小路乗物模型館」の副館長より許可を頂きましたのでご案内致します。模型や乗物好きの方は一度覗いてみてはいかがでしょうか。
このHPの中に「なつかし写真館」というコーナーが有り、右の写真はここに掲載されています。
本来なら「17T」の文字が目に飛び込んで来るところに、水産庁と書いています。
これは知りませんでした。
第十七利丸は、いつのころからか海上水産庁で漁業取締り船として働いていたのですね。

さらに調べてみると、wikipedia の捕鯨船には、「1977年、日本の排他的経済水域が沿岸から200海里に拡張され、その面積はおよそ405万km2と増大した際には、海上保安庁の巡視船の建造が間に合わず、海上保安庁は巡視船を補完する警備救難用船舶の種別として『漁業監視船』を定め、商業捕鯨の縮小で余剰となっていたキャッチャーボート2隻(第二十五興南丸、第十八関丸)を用船した。これらのキャッチャーボートには各2名の海上保安官が乗船し、1年間運用された。また、海上保安庁への用船期間の終了後は水産庁に漁業取締船として用船された。」とあります。
この説明では2隻となっていますが、そんなハズないですよね。
因に日本共同捕鯨キャッチャー・ボート第25興南丸の方は、海上保安庁が用船し漁業監視船(PF01)として塩釜海上保安部に配属。1981年4月1日、解用後水産庁が用船し漁業取締船として使用されたようです。
wikipedia 漁業取締船には「水産庁では、操業の監視や密漁の取締りといった行政警察活動を目的として、6隻の水産庁所有の漁業取締船を保有している。しかし、日本が有する広大な海域を6隻でカバーするのは不可能なため、民間から「やまと」「むさし」「ながと」以下30隻程度の船舶及び航空機をチャーターしており、これらによって、全国の漁場の監視や不法操業の摘発、違法に設置されている漁具の強制撤去処分を行っている。傭船については、船舶の操船は船会社の船員が行い、漁業取締り任務は、乗り込んだ水産庁漁業監督官が行う。船員は、漁業監督官の職務を補助する。」とあります。

おそらく第十七利丸も、左に紹介する第二十三興南丸も、民間として活躍していたのかもしれませんね。
まだ未確認ですが、元日本水産から興南丸が数隻、元極洋捕鯨から京丸が数隻、元大洋漁業から利丸が数隻、その他数隻活躍していたようです。
南氷洋や北洋へ何度も航海していた捕鯨船にとって、打ってつけの任務だったと思われます。
あれ?
やっぱり3色識別ランプがついてないようですね。
上から青・赤・黄の二ずつですから、識別に使うとすればざっと下記の通りか。
左右の位置を考慮しなくても23種ありますね。でもここで気づきました。風呂屋の煙突を。
見る場所や角度によって、煙突が一本に見えたり二本に見えたりするあの煙突を。
キャッチャーボートが横向きだと各色2個の意味がなくなり、分かりずらいですよね。
捕鯨オリンピック全盛期のころは1船団にキャッチャーボートが15隻ほど同行しているので、2船団で30隻となり、その上他国船や同業他社を入れるとこの方法では無理ですね。
少々時間がかかっても、無線を使う方が確実でしょう。
と、
ここまで書いていたのですが、
水産庁漁業取締り船“第十七利丸” と“第二十三興南丸” の写真を撮っていた「末小路乗物模型館」から、またも貴重な写真を見せて頂きました!
私にとっては、ここ数年探し求めていた写真です。
そう、三色×2のランプがついているキャッチャーボートの写真です。


ほらね♪
感謝感激です!
三色ランプ、あったんですねぇ~。
しかも大洋漁業ではなく、日本水産の「興南丸」です。
きっと、各社で三色ランプを使っていたのでしょう。
そっか、色を変えれば会社の識別も可能かもしれない。
写真の「興南丸」は、日本水産の捕鯨母船であった図南丸や橋立丸と一緒に、暴風圏を突破して、凍てつく南氷洋で働いていたのでしょう。

竹田船団長
南氷洋の氷山
想い出 実はですね。昭和40年代にマブチ14を搭載した水中モーターが流行っておりました。やりたくなりませんか?おやじが作った第17利丸に水中モーターを^^
母親が出かけたスキを狙ってそう思ったのですが。。。その時感じたんですよね。自分が作るプラモデルより価値がある事を。