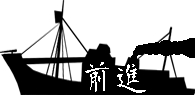お や じ の ア ル バ ム

日新丸 赤道祭 100m競争 騎馬戦 竹馬 ムカデ競争
おやじメモより
三日目の100m競争
船の上で100m競争やってるとは思いませんでしたね。
どの捕鯨母船でも全長100m以上あるので出来ない事はないにしても、やはり、解り易くて盛り上がるのでしょうか。
全国から乗組員が集まっているなかでは、それぞれの呼吸合わせも含めて、運動会はいい効果を発揮していたのかもしれませんね。
赤道祭の三日目。運動会で騎馬戦やってますね。
運動会と言えば騎馬戦。騎馬戦といえば運動会ですが、その歴史は明治時代のようです。
玉木正之のこどもスポーツ研究所によると、運動会が始まったのは明治時代まで遡ります。当時の文部大臣が「運動会を開きなさい」という命令を出した事にはじまるようです。

おやじメモより
左右に別れての騎馬戦
では、騎馬戦が行われるようになったのはなぜか?
明治時代。国会が無かった時代に国会を開くことや憲法を作ることを主張した政治運動・自由民権運動がルーツだったそうです。
当時は政府の力が強く、政府に反対する人たちは、意見を堂々と言うことができなかった。街なかで演説することも、デモ行進も法律で禁止されていました。自由民権運動のメンバーもそれが悩みのたねだった。どうやって自分たちの主帳を聞いてもらおう? 彼らは考えた末、運動会に目をつけました。「運動会をするのなら演説でもないし、デモでもないから大丈夫だろう」と。
そこで自由民権運動をしていた人々(壮士と呼ばれている)がつくった運動会(壮士運動会)で生まれた種目が「政権争奪騎馬戦」と「圧政棒倒し」なのです。騎馬戦ではだれが政治のリーダーになるかを競う姿をゲームにしたもの。棒倒しは当時の政府を倒す意味をこめて棒を倒すもの。すべては競技にまぎれて彼らの言い分を国民に聞いてもらうためだったのです。また、「議会をつくれ」「政府反対」とか言いながら、パフォーマンスを行ったりもした。現在の仮装行列はここが始まりだという。
ところが昨今は、少子化問題などで行われなくなってきているようです。
解らなくもないけど、どうやら本当の理由は人数ではなく、学校や先生の安全の為に行われなくなったいるようです。
少子化は国にとって、ボディーブローですね。
wikipediaによると
問題点
最近は少子化の影響や、以下にあげるような状況から、競技としての騎馬戦は縮小が進んでいる。
競技の中では、棒倒しと並んでもっとも危険な部類に入り、安全面の観点から取りやめているところもある。中学生や高校生ともなると激しい戦いが展開され、審判役を務める教師にも制御することが難しくなる場合が多い。過去には脊椎損傷など重度の身体障害を負った者もいる。県立高校の運動会で騎馬戦が行われた際、同時に複数の騎馬が折り重なって倒れた際、重傷を負った事件について安全配慮義務違反の判決が出されたこともある。
最近では男女共同参画の観点から、小学校などでは女子と共同で行わせる場合もあるが、その場合は女子を保護するためにルール上の制約が大きくなり、競技としての面白味が大きく損なわれるという欠点を含んでいる。
一部では男女混合で騎馬を構成する場合に、発育途上の競技者が体を触れ合うことについて、性教育やジェンダーフリー教育に慎重な保守的立場(産経新聞や世界日報など)から懸念する意見がある。
東京都教育委員会などは通達を出してまで、学年混合戦制を抑制したり競技方式を検討させるなどの方法をとっている。しかし、伝統的な競技であるために、これらの制約には不満の声も聞かれる。
男女平等?性教育?ジェンダーフリー教育?
最近の先生方は、目の前にいる子供達の男女の違いが解らないんですかね。
子供達の人生にどう責任を感じているのでしょうか?
と、さまざまなニュースを見るたびに感じます。

おやじメモより
各県チームのリレー
竹馬競争ですね。何県が優勝したのでしょう。
竹馬は中国から伝わったとされていますが、それは文字だけのようです。
中国では一本の竹をまたいで、文字通り竹を馬に見立てて遊んでいたと云いますから、魔女がほうきをまたぐ格好と同じでしょう。
日本でもお祭りなどでは中国式、または極似の形で行われているようですが、日本では春駒と呼ばれます。
では、国内で私たちが知っている竹馬はいつ頃から遊ばれていたのでしょう。
記録によれば、14世紀の南北朝時代に描き出されといわれる(15世紀説もある)、日本漫画の歴史にも登場する作者不明の絵巻「福富草子」の挿絵には「木製の2本足の竹馬」が描かれているという。
私はまだ見てません。
←こちらは、江戸時代に近世風俗史の基本文献とされる守貞謾稿(もりさだまんこう)が描いた百科事典の一部です。
「今の時代、江戸で竹馬というのは 七、八尺の竿に縄を持って横木をくくりつけ、足かかりとする。」と書いてあり、図を見ても私たちが知っている竹馬そっくりですね。少なくとも江戸時代にはあったようです。
挿絵をクリックすると原本へ飛びます(守貞謾稿 第二十八巻)。
資料は国立国会図書館オンラインサービスで調べられますが、登録が必要。

おやじメモより
甲板部の力走
ムカデ競争ですね。
これも各部対抗戦だったのでしょう。
呼吸が合わないと大変な競技ですよね。
甲板部が優勝だったのでしょうか。
いずれ南氷洋に着いたらその力は存分に発揮されるのかも知れません。

おやじメモより
柏??大会優勝記念 乗船前の自分 23年度夏 柏木町青年団大会 大坊小学校 捕鯨に行く前に身体を鍛えた
へぇ~っ^^ やるな~^^
この写真はアルバムの中では、ちっちゃく、しかし存在感が有る写真です^^
それにしても何の大会の優勝記念なんだろ?相撲という体型ではないが?
参考資料:国立国会図書館
日新丸 作業課 捕鯨銛
日新丸 赤道祭 相撲大会 その3 優勝!