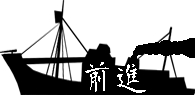お や じ の ア ル バ ム

第七関丸と第一号型第9号輸送艦
おやじメモより
第七関丸 このキャッチャーボートには日本一の砲手泉井さんが乗っている

昭和20年(1945年)11月30日、小笠原諸島周辺での捕鯨が許可(マッカーサーライン)され、第七関丸は昭和23年(1948年)2月15日~5月10日の小笠原近海捕鯨第三次捕鯨に、第一号型第9号輸送艦と共に参加しています。
敗戦後3年ですから、おそらくこの写真の第七関丸ではないかと思われます。
第一号型輸送艦は、大日本帝国海軍の輸送艦の艦級。昭和19年度(1944年)に計画された強行輸送艦で「一等輸送艦」に分類された。当初は「特務艦特型」を略して「特々」と呼ばれ、一等輸送艦に分類された艦級が他に無いため、単に一等輸送艦と呼ばれることが多かった。
日本海軍の公式分類は種別「輸送艦」、等級「一等」、艦型名「第一號型」、艦名は「第○號輸送艦」という。
第一号型輸送艦 wikipedia
第一号型輸送艦の特徴は何と言っても船尾にスロープがあることです。残存艦船の一部は、大発動艇や特殊潜航艇「甲標的」や「回天」を搭載・輸送し、浸水させるために使っていた艦尾のスロープをクジラ用(スリップウエイ)に改良し、船倉に冷蔵庫を増設、中部甲板に鯨油採取のためのプレスボイラーを設置し、捕鯨母船への改装が施された。そして第9号・第16号・第19号は民間の大洋漁業株式会社へ、第13号は極洋捕鯨(日本水産と共同母船)に貸し出され、小笠原近海捕鯨に従事している。
第9号 船歴
昭和19年(1944年)
09月20日 呉海軍工廠にて建造。
10月24日 カガヤン~オルモック間の輸送(多号作戦)に数次成功。
12月01日 マニラ~サンフェルナンド間の輸送作戦に従事、
12月04日 米駆逐艦4、魚雷艇3と交戦。
昭和20年(1945年) 1月に香港経由で本土に物資輸送。
02月21日 横須賀回航。
07月29日 この日まで横須賀~八丈島~父島間の輸送に12回成功。
08月12日 佐伯へ海龍輸送後、呉で終戦を迎える。復員輸送に従事。
昭和22年(1947年) 賠償艦として米軍に引き渡されたが、米国に回航されることなくマルハ太平洋漁業に貸し出され
て、ブルワークや船尾に誘導板を設置して捕鯨船母船として運行。のちスクラップ扱いとして売
却。
昭和23年(1948年) 6月、石川島で解体。竣工以来、幾多の作戦に従事し生き残った武勲めでたい艦。
* 第一号輸送艦は21号まで造船されたものの、殆どが魚雷で沈没。22号は1945年6月23日工事80%で中止。
その後の第七関丸については、高知県出身の弘井武志氏(大正六(1917)年〜昭和五十二(1977)年)の資料の中に、
昭和34年3月に横須賀を出港し、4月に宮城県の牡鹿まで航海していることが
わかりました。
牡鹿といえば牡鹿半島に近海捕鯨発祥と云われる鮎川浜という港があり、昭
和32年(1957年)には当時盛んになっていた小型捕鯨船がすでに10社13隻と
なっていた。
弘井氏が甲種一等機関士の資格を取得したのが昭和34年1月。おそらく南氷
洋から帰港したばかりの第七関丸に機関長として乗り込み、近海捕鯨を兼ねて牡鹿のマルハを目指したのではないかと思われます。
船 名:第七関丸
期 間:昭和34年3月〜4月
職 名:機関長
雇 入 地:横須賀
雇 止 地:牡鹿
船舶所有者:大洋漁業(株)
総 ト ン 数:306.56
泉井守一(いずい・もりいち)
寒さに強いキャッチャーボート
泉井さん
第三天洋丸
泉井さん