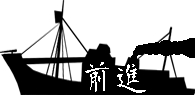お や じ の ア ル バ ム

鎌倉見物
おやじメモより
鎌倉に来てみた
杉田氏 (妹家族と杉田氏の兄[古川氏])

おやじメモより
杉田さんと別れて衣笠駅に立つ古川氏


昭和29年に横須賀線を走っていたであろう70系電車
入港式も終わって、各人が故郷を目指して移動する頃かと思われますが、東京見物や観光地へ足を延ばす人も多かったのでしょう。鎌倉は田浦から近いですし、おやじにとって、この日が鎌倉デビューだ��ったようですね。
鎌倉駅
1889年(明治22年)6月16日 、官設鉄道大船駅~横須賀駅の開通時に、鎌倉駅が開業。神奈川県鎌倉市小町一丁目および御成町にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・江ノ島電鉄(江ノ電)の駅です。
衣笠駅
衣笠駅(きぬがさえき)は、神奈川県横須賀市衣笠栄町二丁目にあるJR東日本の横須賀線の駅で、1944年(昭和19年) 4月1日に国鉄横須賀線の駅として開業。横須賀駅の隣駅です。
横須賀線
横須賀線は沿線に海軍の鎮守府が置かれた軍港都市である横須賀があったことから軍事的な重要路線とされ、早くから複線化などの整備が実施されていた。1922年(大正11年)には、東海道本線東京 - 小田原間とともに電化工事がなされ、翌年の関東大震災により一時中断したものの、翌1924年(大正13年)4月に工事を再開し、1925年(大正14年)7月に完成する。同年12月から電気機関車牽引による客車列車の運転が開始されたが、その後の沿線人口が増加して輸送量も増え、それに伴う列車本数の増大から電車の導入が有利であるとされた。さらには1930年(昭和5年)に開業した湘南電気鉄道への対策も考慮し、横須賀線列車の電車への置換えが計画された。
年表
1889年(明治22年) 6月16日、 大船駅 - 横須賀駅間を開業。
1904年(明治37年) 5月1日、 田浦駅開業。
1909年(明治42年)10月12日、国有鉄道線路名称設定により、
横須賀線となる。
1925年(大正14年)12月13日、大船駅 - 横須賀駅間電化。東京
駅 - 横須賀駅間で電気機関車運
転開始。
1927年(昭和2年) 5月20日、 北鎌倉仮停車場開業。
1930年(昭和5年) 3月15日 、 電車運転開始。
4月1日、 マイル表示からメートル表示に変更(10.0M → 15.9km)。
10月1日、 北鎌倉仮停車場を駅に格上げ。
1931年(昭和6年) 4月1日、 32系電車を投入、以後約1年で従来の電車を置換え。
1944年(昭和19年) 4月1日、 横須賀駅 - 久里浜駅間 (8.0km) 延伸開業。衣笠駅・久里浜駅開業。
1945年(昭和20年) 4月、 横須賀駅 - 衣笠駅間に軍事停車場の相模金谷仮乗降場を開設。
8月、 終戦に伴い相模金谷仮乗降場廃止。
1952年(昭和27年) 3月15日、サンフランシスコ講和条約の発効を前に連合軍専用車が廃止されたが、その時点で横須
賀線には20両(うちサハ48形14両)の代用車が残っていた。
4月1日、 東逗子駅開業。1952年(昭和27年)
1963年(昭和38年)11月9日、 横浜市鶴見区にて横須賀線上下線電車と貨物列車の多重衝突事故(鶴見事故)が発生。
乗客ら161名死亡、負傷者120名を出す惨事となった。
1968年(昭和43年) 6月16日、大船駅付近で電車爆破事件が発生。乗客1人死亡、14人が重軽傷名を出す惨事になた。
1974年(昭和49年)10月1日、 横須賀駅 - 久里浜駅間の貨物営業廃止。
1976年(昭和51年)10月1日、 東京駅 - 品川駅間の別線(地下線)開業。総武快速線が品川駅まで乗り入れ。
芥川龍之介
1915年(大正4年)10月、代表作の1つとなる「羅生門」を発表する。
1916年(大正5年)12月、海軍機関学校英語教官を長く勤めた浅野和三郎
が辞職したのに対し、畔柳芥舟や市河三喜ら英
文学者が浅野の後任に芥川を推薦した。芥川は
海軍機関学校の嘱託教官(担当は英語)として
教鞭を執った。
1919年(大正8年)3月、 海軍機関学校の教職を辞して大阪毎日新聞社に
入社(新聞への寄稿が仕事で出社の義務はな
い)、創作に専念する。
同年3月12日、 友人の山本喜誉司の姉の娘、塚本文(父塚本善
五郎は戦艦「初瀬」沈没時に戦死)と結婚。
同年5月、 「蜜柑」を発表。

この「蜜柑」という作品は、芥川龍之介が海軍機関学校にて英語を教えていた頃の体験だと言われています。
まだ蒸気機関車だった頃の横須賀線で、芥川以外は誰もいない二等室へ小娘が飛び乗ってくる。小娘は窓を開けようとするが思うように開けられない。徐に動き出した汽車は、やがてこの辺り特有の地形が持つトンネルへ突入する。その直前に窓が開いた。
お時間がある方はこちらで読めます。
鎌倉
鎌倉や鎌倉時代については幾重にも歴史が重なっているので、ここでは書ききれません。おまけとして動画を一つ紹介します。
動画:その時歴史が動いた 「大帝国の野望 博多に散る 大陸から見た蒙古襲来」 (2005年)
はて、日本は成長しているのか。
敗戦後、日本の鉄道はガタガタになっていた。敗戦前に米軍の戦略によるに空
爆で破壊もされていたが、列車が老朽化しても修理する力がなかった。その上わ
ずかに残っていた程度の良い車両はGHQに持って行かれたので、結局ボロボロの
車両を使うしかなかった。当然、整備不良による列車事故が増える。
敗戦前には武器や兵隊を運んでいた列車でしたが、敗戦後は食料や疎開先から
戻る人々の輸送、引き上げて来た旧日本兵の輸送などで需要が高まっていた。
戦後2〜3年は石炭事情も悪く、運転本数も大幅に減らされた。
そんな時代背景の中で左の写真は、いわゆる「買い出し列車」
の様子です。窓から出入りする者や、屋根に乗っている者もいた
ようです。
東海道本線でも、関東 - 関西を結ぶ列車は存在せず、下りの長
距離列車は、朝に東京を出る博多行きと、夜に東京を出る門司行
きの2本という状態で、東北本線に至っては、下りの上野 - 青森直
通列車は存在しないというありさまだった。それでもGHQ占領下
では、昭和21年から連合軍のための専用列車を走らせていた。
おもなGHQ専用列車の愛称
「Allied Limited」(アライド・リミテッド、「連合軍特急」)
「Dixie Limited」(ディキシー・リミテッド、「南部特急」)
「Yankee Limited」(ヤンキー・リミテッド、「北部特急」)
「Osaka Express」(オオサカ・エクスプレス、「大阪急行」)
「BCOF train」(ビコーフ・トレイン、「英連邦軍列車」)
「Rest Camptrain」(レスト・キャンプトレイン、「休暇客列
車」)
切断されていた鉄路がようやく繋がり、戦後復興が動き出した昭和23年、
GHQの指令により進駐軍専用列車の車両として寝台列車マイネ40形が新造
される。冷房付き列車として21両が完成した1等寝台車ですが、後に日本の
列車にも使用された。
昭和25年、特別急行列車「へいわ」が復活し、列車名を「つばめ」に改
め、姉妹列車として「はと」も運転が開始された。
昭和26年、東京から日豊本線を経由して都城まで走る急行「阿蘇」や、
山陰本線経由で大社線の大社(1990年4月1日に廃止)まで運転される「い
ずも」など、何本か東京との直通列車が新設される。
昭和27年、サンフランシスコ平和条約が4月28日に発効され、占領状態が
終わると、部分的に日本人にも連合軍特別列車の乗車券を販売するようになった。
この間の捕鯨船団乗組員達はどうやって横須賀まで移動していたのか、相当大変だったと思われます。
日本人に完全開放されたのは1954年(昭和29年)10月1日からですから、昭和29年4月は鎌倉見学の後、特殊列車で弘前を目指したいたはずです。ひょっとすると食糧難を解決すべく南氷洋捕鯨を遂行していた捕鯨会社は、乗車券購入について優遇されていたのかもしれませんね。そうでもないと全国から人員を集められません。
丸山シチュウジの息子さんとの会話で、こんな話題が出てきました。
「東北はまだ東北本線があり奥羽本線があるでしょう。親父曰く『石川県の人も横須賀に来ている。どうやって来るのか。大変な思をして来ているのだろう』と言ってました。」と。(2015.8.13)
確かに、2015年(平成27年)3月14日から金沢ー東京間は北陸新幹線で、約2時間半で結ばれました。それまでは東京ー金沢間を走る直通列車はありません。在来線で5通り程の行き方がありますが、約8〜10時間かかりました(2014)。昭和20年代となると、どうだったのでしょう。



東京駅にあった連合軍専用案内窓口

�東京駅にあった連合軍専用出入口
昭和23年
1948年制作 「立ちあがる輸送」 国鉄戦災復興の記録
昭和28年
1953年制作 「生まれかわる客車」 国鉄客車鋼体化の記録
昭和31年 国鉄
宮城県の瀬峰駅、昭和24年10月1日のアイオン台風被害のため仙北鉄道築館線休止。この時のアイディアがいい。
青函連絡船
Yankee Limited
原節子
入港祝い