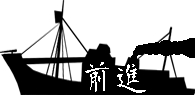top of page
お や じ の ア ル バ ム

クロー

おやじメモより
解剖される鯨体の尾
甲板部は作業員の解剖に従って血流と化し 一頭分は約二十分乃至二十五分で解体の早技一魂も無くなる
日本捕鯨教会 捕鯨の歴史によると、クローは1932年(昭和7年)に登場した道具のようです。
大型の鯨を母船に引き上げる際に、鯨の尾羽(尾びれ)に引っかける漁具。
現在のミンク鯨の捕獲調査では使用されていないが、シロナガス鯨やナガス鯨を主な捕獲対象としていた時代には、スリップウェーの機能を強化し渡鯨作業に重要な役割を果たしていた。
重さ約3tのクローの開発により、大型鯨を母船で解体するのが容易になった為、捕鯨母船そのものも大型になりました。

クロー (重さ3トン)
この大きなクローで、鯨の尾羽のつけ根を挟み、母船々尾の鯨引揚げ斜路から解体甲板まで引揚げる時に使うものです。
洋上でこの作業には大変な技術を要し、甲板長合図のもとに熟練した甲板員の操作するウインチ(揚鯨機)3台によって4人が一体となって当たります。このクロー掛けは仲々の難行だと言われています。
日本の古式捕鯨発祥の地といわれる和歌山県東牟婁郡の太地町。町立くじらの博物館は有名ですよね。
展示されていた捕鯨船第十一京丸が引退し、平成24年2月に第一京丸に代わりました。
クローは第一京丸の手前に展示されています。
左は旧案内板の手書き文字を
打ち直したものです。おそらく
第一京丸に合わせてだと思いま
すが、最近は奇麗な案内板が設
置されているようです。
右は作業風景です。
旗を持って写っている人が
甲板長かもしれません。



支点
クローの写真をじっくり見ると、普段誰もが使うハサミでいう支点に滑車がついてますね。この滑車にワイヤーを通して3tもあるクローを吊り上げていたのでしょう。うまく鯨の尾に乗せたら、引き揚げ用のワイヤーを引っ張れば(1本50t巻)、自動的に鯨の尾を挟められそうですね。
←マウスを乗せるとクローが閉じます。多分、こんな感じで動いていたでしょう。
ワイヤー1本50tのウインチを三台使っていたとすれば、単純に150tの鯨を巻き上げられそうですが、白長須鯨の場合は大きいと180tにもなります。クレーンのように空中へ持ち上げるわけではないから、なんとか成るのかな?
参考資料:日本捕鯨教会
命中!
日新丸のスリップウェー 白鯨
くじらの赤肉
日新丸 船尾
巻き上げられる抹香鯨
解体風景
bottom of page