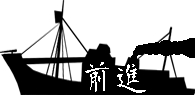お や じ の ア ル バ ム

錦城丸船尾 から 旧横須賀軍港 タンカー
おやじメモより
昭和31年4月2日横須賀港、錦城丸船尾にて
見えるタンカー船はオランダー船、背後の山��は旧横須賀軍港の跡
(荷役中)
第10次南氷洋捕鯨が終わり、横須賀港に停泊中の錦城丸で撮った記念写真なのでしょう。
左:国鉄で横須賀勤務になっていたおやじの友人の奥さん
:おやじの妹
:妻
:おやじ

←それにしても、タンカーって、こういうのじゃないの?
背景に写っているタンカーって、妙に小さいですよね。
調べてみたらそれもそのはずでした。
どうやらタンカーは、1955年(昭和30年)までは大きいものでも6万トン以下だったようです。
←スエズ運河 (クリックするとズームします)
このスエズ運河がタンカーの大きさを決めていたようです。
タンカーに限らず、スエズ運河は紅海と地中海を結ぶ重要な運河であり、アジアとヨーロッパ間をアフリカ大陸を回らずに結ぶ近道として非常に価値が高い運河です。
歴史は紀元前1897年まで遡り、エジプト第12王朝ファラオのセンウセルト2世や3世がナイル川と紅海を繋ぐ運河の建設に乗り出したと言われています。但しこの時代はティムサ湖も海域でした。
歴史は近代に入り、1869年11月。ポートサイドと南端のスエズ市を結ぶスエズ運河が開通しました。スエズ運河は水位を調整する門がないのが特徴です。
建設当初のスエズ運河は全長164km (102mile)、深さ8m (26feet) でしたが、その後何度か拡張工事され、2010年段階では全長193.30km (120.11mile)、深さ24m (79feet)、幅205m (673feet) となったようです。
スエズ運河では、バイパスや湖などの5カ所意外では船舶のすれ違いが出来ません。殆どの場所が南北交互に方向を変える一方通行となります。そういう事情からスエズ運河では、グループ(10-15隻程度)ごとに航行し、単線で運行されている電車が駅で相手を待つのと同じように、バイパスや湖で向かってくるグループの到着を待って、その後先へ進みます。


スエズマックス
スエズマックスとは通行出来る船舶の基準です。現代では喫水20m (66feet) 以下または載貨重量数240,000トン以下かつ水面からの高さが68m(223feet) 以下、最大幅77.5m(254feet) 以下となっています。
昭和30年の頃(上限規制は載貨重量43,000トン型)よりは大きくなってますが、それでも大型タンカーは航行できません。
また、昭和30年はまだまだタンカーが大型化しておらず、第二次世界大戦中に米国が量産していたT2タンカー(約1.65万t)クラスが主流だったようです。
大戦後も、こうしたタンカーは数十年にわたり商
業目的で使用され、多くは国際市場で取引されてい
ました。
その一方で昭和30年には、5.5万トンのタンカーが
誕生します。
主なタンカーの大きさ (1908-1958)
1908年(明治41) 虎丸、531総トンで油槽容量は400トン、大阪鉄工所櫻島製による日本初のタンカー。
1922年(大正11) 干珠丸 、8,200重量トン、129m。
1931年(昭和 6 ) 帝洋丸 、13,960重量トン、150m。
1938年(昭和13) 黒潮丸 、14,960重量トン、153m。
1951年(昭和26) 日章丸(二世)、18,774重量トン、IHI呉、出光興産。
1955年(昭和30) シンクレア・ペトロ・ロア 、55,000重量トン、全長230m。
1956年(昭和31) ユニバース・リーダー 、85,500重量トン、全長248m。
1958年(昭和33) ユニバース・アポロ、103,000重量トン、全長287m、IHI呉。
世界初の10万トン級タンカーです。

さて、こんなに便利なスエズ運河ですが、1956年(昭和31年)10月29日、イスラエル軍がエジプトに侵入して第二次中東戦争が勃発すると、翌10月30日、エジプト軍がスエズ運河を通航不能にしてしまいました。これが因と成ってどの船も近道できなくなったわけです。
止むを得ずアフリカを迂回する事になったことで、輸送効率を上げるためにタンカー主達が大型化を進めます。これによってスエズマックスから解放された造船業界は、大型タンカーの造船に力を注ぐことになります。
そのおかげで多くの船を手がけた日本が、英国を抜いて「世界一の造船大国」と云われるようになるのです。
世界一大きいタンカー
1950年代のうちに10万トンを超えたタンカーが60年代には20万トン級が建造されます。
1962(昭和37)年7月10日進水「日章丸(三世)」13万1,000重量トン、全長291m、佐世保重工、出光興産。
幅43m。 深さ22.2m。航海速力16ノット。出力2万8千馬力。
1966(昭和41)年「東京丸」15万3,687重量トン、全長306m、IHI横浜、東京タンカー。
1966(昭和41)年就航「出光丸」21万重量トン、全長342m、IHI横浜、出光興産。世界初の20万トン級タンカーです。
70年代に入ると30万トン級、40万トン級、50万トン級へと進化します。
1971(昭和46)年4月進水 日石丸、37万2,400重量トン、347m、IHI呉、東京タンカー。
1972(昭和47)年 グロブティック・トーキョー、48万3,644重量トン、全長379m、IHI呉。
1975(昭和50)年 日精丸、48万4,276重量トン、全長378.35m、IHI呉、東京タンカー。
238,517.49G/T、型幅62.00m、型深36.00m
1976(昭和51)年 バティラス、54万2,400重量トン、全長400m フランス
1979(昭和54)年12月3日 シーワイズ・ジャイアント、42万重量トン、全長377m
80年代、シーワイズ・ジャイアントが船体延長されました。
船歴
1979年12月3日 住友重機械追浜造船所で竣工
1980年7月~12月12日 日本鋼管(NKK)津製作所で船体延長。
重量トン数:42万(422,039DWT)から
56万(564,763DWT)重量トンへ
総 ト ン 数:189,110GTから260,851GTへ
全 長:377mから458.45mへ
幅 :68.8m 変更なし
これで世界最大の船舶となる(総トン数ではバティラス級の方が大きいので5位)。
1988年 イラン・イラク戦争で損傷。


1989年 「ハッピー・ジャイアント」[Happy Giant]と改名。
1991年 「ヤーレ・ヴァイキング」[Jahre Viking]と改名。
2004年 「ノック・ネヴィス」[Knock Nevis]と改名。FSO(浮体式海洋石油・ガス貯蔵積出設備)として使用。
2010年 解体
この当時日本でも、100万トン級タンカーの計画があったようですが、タンカーの大型化はシーワイズ・ジャイアントをピークに次の時代へ入ります。そして日本は、1986年(昭和61年)のバブル景気に突入してしてゆきます。
造船技術が上がった現代では、燃費向上、人員減少、海峡通過、輸送コスト、リスク管理などから30万トン級が主流になっているようです。
マラッカ海峡を通り、最短オイルロードを使うには、それぐらいの大きさが丁度良いということでしょう。
現代のオイルロード
News2u.net(2012年04月06日)によると「近い将来、オイルタンカーの燃料効率やバラスト水処理システムに関する規制が施行される見通しで、企業はタンカーをアップグレー
ドするか、改造する必要があると予想されます。」
これでまた日本が造船で稼げるようになるといいですね。因にタンカーの寿命は20年位だそうです。
しかし2015年、日本が造船で景気が良くなったという話は聞こえてこないですね。
さてさて、おやじの写真に写っている船をネット上で調べた結果、一番近そうなのがこれでした。
オランダの「アクセルダイク(貨物船)」です。
船歴
1945年2月進水したアメリカ軍用の戦時標準船ビクト
リー・シップの「コルビー・ビクトリー」をオラン
ダ・アメリカライン社が1947年購入し運用した貨物
船。
1965年6月にパナマへ売却、リベリア船籍「モニーク」
となった。
1971年台湾にて解体。
(↑船舶模型 Modelship.jp 写真をクリックすると飛びます)
タンカーとは液体を運ぶ船という意味なので、おやじの写真に写っている船が液体を運んでいればタンカーですが、よく見るとクレーンが多い気がするんですよね。T2タンカー系かとも思いましたが、どうやら貨物船のようです。あるいは日本で貨物船になったのか、ですね。
旧横須賀軍港の跡については、おそらく現「ヴェルニー公園」付近のことを言っているだろうと思われます。
この公園は1946年(昭和21年)に「臨海公園」として開園しました。
2001年(平成13年)にフランス式庭園の様式を取り入れてリニューアルオープンした時に「ヴェルニー公園」と命名されたようです。名称は横須賀造兵廠その他の近代施設の建設を指導し、日本の近代化を支援したフランス人技術者レオンス・ヴェルニーに由来します。
この公園の中に、かつての旧軍港への入口として多くの軍人が行き交った旧横須賀軍港逸見波止場衛門が有ります。
もし、錦城丸が逸見波止場衛門の方向を向いていたとしたら、下記のような場所から写真を撮ったのではないかと思われます。横浜ベイスターズ総合練習所が有るのもミソですね。その昔、この場所は大洋漁業の倉庫が有った場所であることが分かりました。母船の停泊場所は長浦港側だけではないようです。

大洋漁業と野球の歴史
●1949年(昭和24年)11月 プロ野球球団「まるは大洋球団」を結成し、セントラル・リーグに加盟。
●1950年(昭和25年)7月 大洋漁業株式会社が株式会社林兼商店を合併。「まるは大洋球団」を「大洋ホエールズ」に改称。
●1993年(平成5年) マルハ株式会社と商号変更。「大洋ホエールズ」球団を「横浜ベイスターズ」に改称。
この辺に捕鯨母船を停泊させて、倉庫から資材を大発で運んでいたのかも知れませんね。
次回横須賀へ行く事が有ったら、是非山を見てみたいですね。
参考資料
wikipediaでタンカー、T2 タンカー、スエズ運河、ノック・ネヴィス、ヴェルニー公園、横浜DeNAベイスターズ総合練習場、
●世界の写真 船旅でだけ、体験できる風景よりスエズ運河(アスカ2)
●出光タンカー株式会社
●全国内航タンカー海運組合
●共栄タンカー株式会社
●「シーワイズ・ジャイアント」[Seawise Giant]
●文部科学省
●戦後建造大型タンカー技術発展の系統化と資料調査 - 国立科学博物館 pdf
●オランダ アクセルダイク(貨物船)船舶模型
●News2u.net
●ここは横須賀
●横須賀市 旧海軍軍需部と長浦
シティーズ サービス マイアミ号
家族
愛妻と