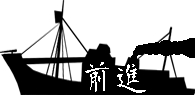お や じ の ア ル バ ム

氷山 ペンギン城 はくや
おやじメモより
ペンギン城 毎日明るく夜がない だから太陽は同じところにいるようだ。
白夜(はくや)という事でしょう。
太陽が横に動いて沈まない。どんな気分になるのでしょう。体内時計が狂ってしまいそうですね。
日常身につけた感覚では、太陽と共に一日が始まり、夜は睡眠で元気を充填し、また太陽と共に一日が始まる。しかし、極点では1年かかることになりますね。
当にここは極寒地獄。
白夜 (はくや) が白夜 (びゃくや) になった訳
背景としては、まず俳優兼歌手だった森繁久彌さんが1960年(昭和35年)に映画『地の涯に生きるもの(原作は戸川幸夫の小説「オホーツクの老人」)』の撮影で北海道の知床半島羅臼(らうす)を訪れた事から始まります。撮影が終わって羅臼を去る昭和35年7月17日、地元の方々の前で『さらば羅臼よ』という曲名で大合唱する。原曲は「オホーツクの舟歌」とされているが、、、
Yomiuri On-Line 北海道発 知床特集 によると、「羅臼村(現羅臼町)の200人近い村人たちがエキストラを務め、中には本当の遭難者の遺族もいた。森繁さんに呼応するように泣き叫んだ。『撮影が終わっても、泣き声がやまない。みんなが家族同然で、監督もカメラマンも、もらい泣きした』。当時、村財政係長で、ロケ隊の受け入れ、エキストラの確保に奔走した志賀謙治さん(85)は述懐する。
森繁さんは港で「映画や芝居で涙は流すが、今回ばかりは心底泣かされた」と、大声で村人に感謝の気持ちを伝えた。」
前夜から「いい歌ができた」と喜んでいた森繁さんは、翌日の午前8時過ぎ、別れを惜しんで集まった400人ほどの村人の前に、ギターを抱えた蝶(ちょう)ネクタイ姿で共演の草笛光子、司葉子さんらと並んだ。「今、日本の国では、人情が紙より薄いと言われていますが、羅臼のみなさんの人情の機微に触れさせてもらって誠にありがとうございました。後々(のちのち)のために歌を作りました。みんなで歌って別れましょう」と、そう話した森繁さんが模造紙の歌詞を示し、ギターを弾いて歌った。志賀さんは、持っていたカメラのシャッターを押した。「君は出て行く 峠を越えて」。森繁さんは、小節ごとに繰り返して教え、やがて歌声は村人、ロケ隊全員の大合唱となった。
ということは、羅臼村(当時)の人々との別れの歌(さらば羅臼よ)を元々ある「オホーツクの舟歌」のメロディーにのせて、いわゆる替え歌を歌ったのかと思っていたら、城島明彦(作家)の『ちょっとあぶない雑記帳』によると「『さらば羅臼よ』は昔から地元で歌われてきた曲だったが、うろ覚えの人が多く、詞も曲も不確かだった。それらを取材し、採譜し、採詞したのは吉松安弘という東大出の助監督であった。」
と云う事らしい。
だとすれば、「さらばラオスよ」も「オホーツクの舟歌」のメロディーも、地元の皆さんと吉松安弘氏の努力の結果ということになりますね。
さらにこの曲は歌詞を変えて1962年、大晦日の東京宝塚劇場にて行われた第13回NHK紅白歌合戦に森繁さんが出場し、作詞・作曲 森繁久弥「知床旅情」として紹介され、広く日本国民が知る事となる。

栄屋旅館の玄関に張り出された
さらばラウスよ
知床の岬にはまなすの咲く頃
思い出しておくれおれたちのことを
飲んで騒いで丘にのぼれば
遥かキナシリに白夜はあける
旅の情か酔ふほどのにさまよひ
浜に出て見れば月は照る波の上
君を今宵こそ抱きしめんと
岩かげによればピリカが笑う
別れの日は来たラウスの村にも
君は出てゆく峠をこえて
忘れちゃいやだよ気まぐれ烏さん
私を泣かすな白いカモメを
1960年 オホーツクの舟唄
歌:倍賞千恵子
1976年2月2日第一回徹子の部屋
オホーツクの舟歌 歌:森繁久弥
知床旅情 歌:森繁久弥
知床旅情
作詞・作曲 森繁久彌
知床の岬に はまなすの咲く頃
思い出しておくれ 俺たちのことを
飲んで騒いで 丘に登れば
はるか国後に白夜(びゃくや)は明ける
白夜論争
実際には、北海道で白夜(はくや)になる
事はないのです。国後でも無理です。やは
り東京感覚なんですよね。オホーツクの舟
歌にある「哀れ東にオーロラかなし」は、
昭和33年に見られたようですが、東ではなく
北だと思われます。
本当は白夜(はくや)ではないので、良心か
ら白夜(びゃくや)と歌ったのか、単純に知らなかったのか、歌い易かっただけなのか、二年前に封切られたルキノ・ヴィスコンティ監督の映画「白夜」に「びゃくや」と読みがつけられていたからなのか定かではありませんが、有名人が白夜(びゃくや)といえば、日本中が白夜(びゃくや)になってしまうアタリ、日本ですよね。
国語学者であり、民俗学者、随筆家であった故・池田彌三郎氏が、森繁さんに「正しくはハクヤだ」と言ったそうだが、逆に「そんなら、白虎隊はハッコタイかい?」と反論されて終わっているようです(トクダス)。
今ならネットで炎上しそうなこの話も、昭和35年はまだまだ家に黒電話があれば金持で、テレビはカラー放送元年であるものの一般家庭では白黒が主流。この年、日立製作所が国産カラーテレビ「ポンパ」を発売。キャッチコピーは「色は日立の御家芸」でした。(昭和45年にポンパ号が走る)
現代のように誰でも世に意見を配信することなど考えられなかった時代です。テレビとラジオで同時中継された紅白歌合戦。しかもこの年は視聴率80.4%でしたから、そりゃ~テレビに登場すれば一発公布されますよね。
この日からハクヤはビャクヤになりました。
昭和45年の再ブレーク以降、NHKは「びゃくや」を標準読みとします。
詩心という人もいますが、これは次元が違いますよね。
因みに太陽が一日中昇らないことを極夜(きょくや)と言います。
では、なぜ白夜や極夜が起こるのでしょうか?
左図のように左側から飛んでくる太陽光線に対して地球の自転軸が約23.4度傾いているためです。
もし自転のみだったら、北極(北極圏)はいつも夜であり、南極(南極圏)はいつも昼となります。
さらに地球は太陽のまわりを公転しているので、次のようなイメージになります。
実際は自転が約365回に対して公転は1回です。自転速度もほぼ一定であり、一回転約24時間です。
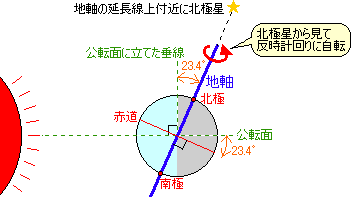
このイメージでは、日本の季節が夏至(6月21日ごろ)から夏→秋→冬→春→夏至と移り変わっています。
日本が冬至(太陽が一番低く昇る12月22日頃)の日、南極は太陽が沈まない白夜となっています。
捕鯨シーズンは夏の南氷洋です。もし、日新丸船団が南極圏に入っていれば、おやじがいうように太陽は沈みません。
動画で見る昭和35年
昭和35年 行きづまる東海道
働く若者
昭和35年日本シリーズ 大毎対大洋
内藤多仲のタワー六兄弟
名古屋テレビ塔(昭和29年開館)、大阪の二代目通天閣(昭和31年開館)、別府タワー(昭和31年竣工)、
さっぽろテレビ塔(昭和32年竣工)、東京タワー(昭和33年竣工)、博多ポートタワー(昭和39年竣工)。
千歳飛行場
昭和34年7月20日、ようやく連合国軍から日本政府に返還さた千歳飛行場は、翌々年の昭和36年9月25日に日本航空が千歳 - 東京間に国内線初のジェット旅客機コンベア880を初就航させた。
そんな時代の昭和35年、関東や関西以南から北海道旅行を楽しむには、汽車と電車とディーゼル車を乗り継いで青森まで行き、青函連絡船で津軽海峡を渡って函館市へ。戦時中、要塞地帯になったことで山全体が軍事機密となり、一般市民の出入りはもちろん地形図からも消されていた函館山へ登り、百万ドルの夜景を楽しんだことでしょう。さらに時間がある方は洞爺湖、札幌と北上し、道内を旅したあとは、殆どの人が「木彫りの熊」をお土産に帰路についたのではないでしょうか。きっと現在の海外旅行なみの旅だったことでしょう。昭和37年の紅白以降は、さらに北海道が注目されたようですね。(1ドル=360円固定レート時代)
タカラが「ダッコちゃん」発売(180円)し、 日産自動車が「セドリック」を発売し、花王石鹸が日本初の住居用洗剤「マイペット」を発売。作れば売れる時代を迎えていた昭和35年でした。

知床ファンタジア
それはオホーツクの海に押し寄せる流氷と厳しい寒さを逆に楽しんでしまおうという知床の冬のイベントです。
「オーロラファンタジー」はそのメイン・イベント。昭和33年に知床の夜空に現れた本物のオーロラの感動を何とか再現したいという想いから生まれました。ダイナミックな音響とレーザーが織りなす幻想空間が知床に出現します。
会場:ウトロ オロンコ岩
南氷洋 南極大陸は誰のもの
氷山 食糧