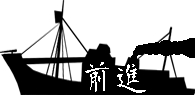お や じ の ア ル バ ム
命中! 白長須鯨 捕鯨オリンピック BWU

おやじメモより
ずんずん引く白長須鯨 潮を吹き乍ら縄を引く(身長16間)
一間とは柱と柱の間という意味で、長さを決める単位ではありません。
一間の長さを決めてから建物を描き、建築するというのが本来の使い方なのです。
よくいわれる江戸間は、1間=6尺。畳の大きさは5尺8寸×2尺9寸
京間は、 1間=6尺5寸。畳の大きさは6尺3寸×3尺1寸5分
という訳で、1間=2mでもいいのです。
一応ここでは1.82mで計算してみましょう。
1.82m×16間=29.12m 白長須鯨にしてはちょっと小ぶりかな。
ロープがピーンと張ってますね。船ごと引っ張られているのでしょうか。
カジキマグロどころの話じゃありませんね。なにしろ地球誕生以来最も大きい動物ですから、、。
と、考えていたのですが、いろいろ調べていたらクジラはカジキマグロと違い哺乳類なので、戦いは15分で終わるそうです。
納得。
だとするとカジキマグロが可哀想かな。3時間の死闘なんてありますもんね。
グリーンピース・インターナショナル本部がオランダのアムステルダムに設立されたのが1979年(昭和54年)10月14日ですから、この時代はまだまだ現れておらず、氷山の陰からゴムボートが現れる事もなく、ただただ敵は他国の捕鯨船だったようです。一頭の鯨を二国のキャッチャーボートが追いかけていたらしいです。そう、捕鯨オリンピック時代なんですよね。
捕鯨オリンピックといえば
17世紀、北大西洋スピッツベルゲン島でオランダとイングランド(イギリス)の武装化した捕鯨船団が戦いながらホッキョククジラを追いかけて枯渇させ、北大西洋に鯨を求めて捕鯨船を南下させた。
18世紀後半、捕鯨を再開したイギリスにアメリカの捕鯨船も加わり、20世紀に入ると大西洋におけるセミクジラとホッキョククジラはほぼ姿を消した。
舞台が太平洋へ移りつつ、一方では大きくて泳ぎが早く死亡すると沈んでしまう長須鯨類は豊富に残っていた。これに目をつけたのがノルウェーで、銛に縄をつけたり、母船にスリップウエイをつけたり、クローを開発したり、母船式近代捕鯨を完成させた。
1929年、ノルウェーが獲るだけでなく繁殖の必要性を考えて「国際捕鯨統計局」を設立。
各国が近海捕鯨から遠洋捕鯨が可能になると、かつて北大西洋がそうだったように、一つのエリアで複数の国の捕鯨船団が争う事になり、最早それぞれの国法では管理できない状態になった。そこで必要になるのが国際ルールだが、捕鯨オリンピックでは全体の目標数値しか決めません。つまり、シーズン中にどの国の捕鯨船が何頭獲ってもかまわないが、各国 (ノルウェー、英国、ソ連、米国、日本など) の捕鯨船は国際捕鯨統計局に捕獲頭数を随時報告し、各国の合計が目標に達した時点で全体停止するというルールなのです。一頭でも早く獲ったものが勝ちなのです。それはそれは各国各社の捕鯨船は頑張りますよね。
20世紀半ば、終戦を迎えて母船式捕鯨を復活させた日本は、戦後の食料難を解決すべく南氷洋へ向けて出港したのでした。
このオリンピック方式は1959年(昭和34年)まで続きました。
BWU(Blue Whale Unit - シロナガス換算方式)
次 期
第 1 次南氷洋捕鯨
第 2 次南氷洋捕鯨
第 3 次南氷洋捕鯨
第 4 次南氷洋捕鯨
第 5 次南氷洋捕鯨
第 6 次南氷洋捕鯨
第 7 次南氷洋捕鯨
第 8 次南氷洋捕鯨
第 9 次南氷洋捕鯨
第10次南氷洋捕鯨
第11次南氷洋捕鯨
第12次南氷洋捕鯨
第13次南氷洋捕鯨
第14次南氷洋捕鯨
第15次南氷洋捕鯨
第16次南氷洋捕鯨
第17次南氷洋捕鯨
第18次南氷洋捕鯨
第19次南氷洋捕鯨
第20次南氷洋捕鯨
第21次南氷洋捕鯨
第22次南氷洋捕鯨
第23次南氷洋捕鯨
第24次南氷洋捕鯨
第25次南氷洋捕鯨
第26次南氷洋捕鯨
年号 期間 捕鯨枠
昭和21年 1946/47 16,000 BWU
昭和22年 1947/48 16,000 BWU
昭和23年 1948/49 16,000 BWU
昭和24年 1949/50 16,000 BWU
昭和25年 1950/51 16,000 BWU
昭和26年 1951/52 16,000 BWU
昭和27年 1952/53 16,000 BWU
昭和28年 1953/54 15,500 BWU
昭和29年 1954/55 15,500 BWU
昭和30年 1955/56 15,000 BWU
昭和31年 1956/57 14,500 BWU
昭和32年 1957/58 14,500 BWU
昭和33年 1958/59 15,000 BWU
昭和34年 1959/60 14,600 BWU
昭和35年 1960/61 17,780 BWU
昭和36年 1961/62 17,780 BWU
昭和37年 1962/63 15,000 BWU
昭和38年 1963/64 10,000 BWU
昭和39年 1964/65 8,000 BWU
昭和40年 1965/66 4,500 BWU
昭和41年 1966/67 3,500 BWU
昭和42年 1967/68 3,200 BWU
昭和43年 1968/69 3,200 BWU
昭和44年 1969/70 2,700 BWU
昭和45年 1970/71 2,700 BWU
昭和46年 1971/72 2,300 BWU
西欧諸国では、クジラは油なのです。
しかし、鯨油といえばマッコウクジラではないのか?
シロナガスクジラは大きくて、泳げば早く、死ぬと沈むので、古くは捕鯨の対象ではなかったのだが、近代捕鯨に入ってからは捕鯨対象になり、その理由は効率がいい鯨油確保です。
第二次世界大戦後に設立されたIWCが全体枠をBWU(シロナガスクジラ換算方式)で設定したこともあり、シロナガスクジラは激減の一途をたどった。
シロナガスクジラ換算方式は、どの鯨を捕っても下記のように換算されるのです。
シロナガスクジラ1頭=1BWU
ナガスクジラ2頭=1BWU
ザトウクジラ2.5頭=1BWU
イワシクジラ(戦前は5頭)6頭=1BWU
どこの国の捕鯨船団も、同じ手間ならまずはシロナガスクジラを狙いますよね。シロナガスクジラ換算方式はオリンピック方式が中止された1959年以降も続き、1972年まで採用されました。
IWC(国際捕鯨委員会:事務局はイギリス)発足は1946年でした。
1948年11月10日、国際捕鯨取締条約が有効になリ、寄託者は世界のおまわりさんを公言しているアメリカ合衆国政府です。
南極の四季
北半球の日本とは夏と冬が逆になるので、日本の冬は南極の夏です。捕鯨シーズンは南極の春から秋にかけて行われるので、どうしても年をまたいでしまいます。夏は太陽が沈まず、冬は太陽が昇りません。
第三天洋丸
シロナガスクジラ換算
第7次南氷洋捕鯨
祝花
目標達成
しらさぎ城 第五福竜丸
氷山
出港準備
マッコウクジラ メートル法
ユニオン捕鯨と大洋
日新丸のスリップウェー 白鯨