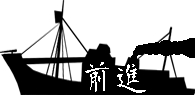お や じ の ア ル バ ム

船のような氷山 船の大きさくらべ 正和丸
おやじメモより
先頃は(2月9日)大吹雪の船団ストップして待機したが、大風も止まり移動するところ
右へ向いている船のような氷山ですね。南氷洋で大吹雪だとブリザードでしょうか。
船の長さ比べをしてみましょう。
「いさなとり」からはじまる日本捕鯨の流れの中で、南氷洋捕鯨や北洋捕鯨の他に小型沿岸捕鯨が発達しました。それに使われる捕鯨船が左下の第二十八大勝丸や正和丸です。それにしても小さいですよね。
小型捕鯨船は47.99t以下と定めがあり、47.5t の第二十八大勝丸は小型捕鯨船の中では大きい方です。また、前部には50ミリ砲1門を備えています。
◎ 捕鯨銛 50ミリ75ミリ90ミリ
2012年度における農林水産大臣より許可された小型捕鯨業で捕獲された鯨の鯨体処理場の設置場所は、つまり小型沿岸捕鯨基地は、北海道の網走、函館、宮城県の鮎川、千葉県の和田、和歌山県の太地の5箇所です。
調査捕鯨船の母港としては、北海道の釧路と山口県の下関がその役割を果たしています。
リンク
豊かなオホーツクに活氣みなぎるまち/網走市
釧路とくじら/釧路市
函館市と捕鯨
日本の鯨食文化ー和田町
日本一のくじらのまち/下関市
石巻百景
水産庁 捕鯨を取り巻く状況
小型沿岸捕鯨の現状 pdf




日本で一番小さな捕鯨船である太地の正和丸。この小さな船体でどうやって捕鯨をするのかと思ったら、活躍するんですね。昔見たアリンコアントを思い出しました。
3.11(2011年)の東日本大震災で津波の犠牲になった石巻市鮎川浜では、捕鯨船2隻が陸に流され、計画の捕鯨が出来なくなりました。その時に助っ人として太地から応援に来たのが正和丸です。捕鯨の調査地点も宮城県沖ではなく釧路沖へ向かいました。
◎ 函館のトピックス(2011年5月25日)より
ツチクジラ初水揚
ツチクジラは体長9m程度の大きなクジラですが、IWCの管轄になっていないため商業捕鯨は禁止になっておらず、水産庁が独自に管理しながら、函館で10頭、宮城県鮎川と千葉県和田浦で52頭、網走で4頭の捕獲枠が与えられ、操業をしています。日本海には1500頭のツチクジラが生息していると推定されており、推定誤差を考慮し増殖率にも安全率をかけ、万全な資源保全を考えて10頭を上限にしています。
函館で操業しているのは、太地漁業協同組合の小型捕鯨船正和丸15.2トン。全長15.1mの小さな捕鯨船ですが、これで9m、10トンの大きな雄のツチクジラを江差沖(開陽丸が沈んだ場所)で仕留め、鮮度を保つために洋上で腹を割いて海水で冷やしながら、9時間
をかけて函館に曳航してきました。
小型沿岸捕鯨では母船式と違い、9時間掛けても捕鯨基地まで運ぶんですね。
ただ、洋上で腹を割いてはどうやって行っているのでしょうか。不思議がまた一つ増えてしまった。
また、移動はどうしていたのでしょう。小型沿岸捕鯨のキャッチャーボートの特徴として後部がトラックの荷台のようになっているので、そこへクジラの尾を乗せて海上を走っているのでしょうか。9mのツチクジラとなると一頭そのままは積めませんよね。しかし、船尾にクジラの尾だけのせるとしても、それでは捕鯨船が
沈みそうですね。謎だ、、。
まさか大型捕鯨船と同じように舷のどこかに縛っているのか?
さらに調査してみる事にしましょう。
それにしても小さな捕鯨船正和丸にとって、ツチクジラはでっかい獲物ですよね。
おまけ
調査結果
やっと見つけました。右の写真を御覧下さい。
2005年の資料ですが、捕獲場所は松前沖約45㎞、体長9.7メートル、体重10トンの雌のツチ鯨です。
やはり捕鯨船に尾を乗せるのではなく、写真のように船舷に尾を固定して運ぶんですね。160馬力の小さな正和丸にとっては大きい負担でしょう。真っ直ぐ進めるのだろうか。
また、小さなゴンドウクジラなどは二頭ぐらい船上にのせて運んでいるようです。
ガンバレ正和丸!

この写真は◎ 太地町漁業協同組合の◎太地町漁業協同組合からのお知らせ 出漁(2005/06/28)のページに掲載されています。
迂回 大氷山
特別編 第十六利丸の事