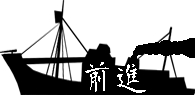お や じ の ア ル バ ム

抹香鯨の好物 ダイオウイカ
おやじメモより
大イカ 抹香の胃袋から 約六尺におよぶ 足端��にわ5cm位のツメがある 1本づつ
胃の中から 厚サ 肉10mm
抹香鯨がこのイカを求めて深海2000mまで潜っているのです。
約六尺とありますから、1尺=(10/33)メートル(約30.3cm)× 6= 181.8cm 。
1m81cmですと、私よりデカイ。
しかし、成長すると20mを超えるというから、ダイオウイカにしては小さいですね。
あまり消化されてないのは、食べてから時間が経ってないからかもしれません。
そして、そのまんま出てきたという事は、噛み切らずにそのまま呑み込んでいるからでしょう。
wikipedia によると、ダイオウイカの日本での発見例は外套長1.8m、触腕を含めると6.5mにもなるという。ヨーロッパで発見されたタイセイヨウダイオウイカ(テイオウイカともいう)で、特に大きなものは体長20mを超えたとも云われるが、生態についてはそれほど知られてなく、とても強い力を
持ち、深海で活発に動き回っているという程度しか判明していない。
ところが近年、少しづつですがいろいろ分かってきました。
2013年1月6日、2004年に小笠原諸島沖の深海で世界初の生きたダイオウイ
カの撮影に成功した海洋生物学者の窪寺恒己、エディス・ウィダー、スティー
ブ・オーシェーらが小笠原諸島父島の東沖の深海で生きているダイオウイカの
動画の撮影に世界で初めて成功したと発表。この模様は2013年1月13日(日)午
後 9時00分~9時58分にNHKスペシャル「世界初撮影!深海の超巨大イカ」と
して放送されました。この映像では、今まで大きい体でゆっくり泳いでいると
思われていたダイオウイカが、深海を巧みに動く姿が撮影されています。
2013年3月20日には、これまで18種類あると言われていたダイオウイカの分
類が、英学術専門誌「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society
B)」で発表された内容によると「研究チームは、オーストラリア、スペイン、
フロリダ、ニュージーランド、日本の海域で発見された43体の死骸を対象に、雌の親から受け継がれるミトコンドリアDNAを解析した。すると、DNAの特徴の差があまりにも小さかったことに驚いたという。『このデータは、世界には1種類のダイオウイカしか存在しないことを強く示している』とチームは述べている。」
(c)AFP
また、2014年に入ると日本海側でダイオウイカが次々と揚がり、原因は専門家でも意見が分かれるところだが、ダイオウイカ研究の第一人者である窪寺恒己博士によると、海水温の変化に問題があるらしい。
ダイオウイカにとって唯一の天敵がマッコウクジラです。マッコ
ウクジラの胃の内容物から本種が発見されることも多く、皮膚に吸
盤の痕跡が残っていたりもする。
ダイオウイカの吸盤には鋸状の硬い歯が円形をなして備えられて
おり、獲物を捕獲する際にはこれを相手の体に食い込ませることで
強く絡みつくと考えられている。しかし、マッコウクジラはこの吸
盤でしがみつかれて体表を傷つけられても、構わずに丸呑みにして
しまうのだそうだ。

ダイオウイカによって刻み付けられた吸盤の傷痕が残るマッコウクジラの皮膚
ダイオウイカの謎は、少しづつ解明されてきたとは言うものの、まだまだ「うなぎ」よりも分かっていないらしい。
では、昔はどうだったのか?
古代より近代まで、漁師や船乗りの間では、海の怪物はただただ恐怖でした。
語り継がれた伝説は
ダイオウイカの敵
海の怪物クラーケンの恐怖
凪(なぎ)で船が進まず、やがて海面が泡立つなら、それはクラーケンの出現を覚悟すべき前触れである。
姿を現したが最後、この怪物から逃れる事は叶わない。
たとえマストによじ登ろうともデッキの底に隠れようとも、クラーケンは船を壊し転覆させ、海に落ちた人間を1人残らず喰らってしまうからである。

2009年に小笠原沖で撮影されたダイオウイカを咥えて泳ぐマッコウクジラ
凪(なぎ)とは、風力0(風速毎秒0.0 - 0.2m)の状態。
一般に日中に吹く海風から、夜中に吹く陸風に切り替わる無風状態を夕凪(ゆうなぎ)といい。陸風から海風へ切り替わるときの無風状態を朝凪(あさなぎ)という。
また地球規模では、赤道無風帯というものがある。
いわゆる地図に描かれている赤道線上ではなく、太陽が一番近い場所では、北から流れてくる貿易風と南から流れてくる貿易風がぶつかり、風が止まります。さらに熱で上昇気流が生まれる場所を赤道無風帯と言います。
人類が船を手に入れてから、船に動力を積み込めるようになるまでは、風と人力で動かしていました。風がなければ船は動けないのです。

クラーケンの正体
← フランスの軟体動物学者ピエール・デニス・ド・モンフォール (en) によって描かれた巨大な頭足類(1801年公表)。
ノルウェー近海やアイスランド沖、ほかにもアフリカ南部のアンゴラ沖などで、このような生物に襲われたという記録が船乗りによって残されている。
もし赤道無風帯で帆船が動けなくなっている時に、海の巨大生物が現れて襲われれば、逃げられないということになりますね。赤道を無事通過できるように赤道祭を行っていたのもうなづけます。
古代から様々な形で伝えられている謎の巨大生物。特にタコやイカの姿で描か
れることが多いが、他にもシーサーペント(怪物としての大海蛇)やドラゴンの一
種、エビ、ザリガニなどの甲殻類、クラゲやヒトデ等々の絵が残されています。
姿がどのようであれ一貫して語られるのはその驚異的な大きさであり、「島と間
違えて上陸した者がそのまま海に引きずり込まれるように消えてしまう」といった
種類の伝承が数多く残されています。

←フランスの船乗り達がアフリカのアンゴラ沖で遭遇したという海の怪物を基に、ピエール・デニス・ド・モンフォールがクラーケンとして描いたもの(1810年公表)。

↑ 同じく、アンゴラ沖のクラーケン。ピエール・デニス・ド・モンフォール、1810年公表。

日本での伝承
日本では赤鱏(あかえい)の島や海坊主などが伝承されている。
赤えい
安房国(現在の千葉県南端)の野島崎から出航した舟が、大風で遭難して海を漂っていたところ、島が近くに見えてきた。これで助かったと安堵した船乗りたちは舟を寄せ、上陸した。ところが、どこを探しても人がおらず、それどころか見渡せば、岩の上には見慣れない草木が茂り、その梢には藻がかかっている。あちこちの岩の隙間には魚が棲んでいる。
2、3里(およそ10キロメートル前後)歩いた
が人も家も一向に見つけることができず、せめて水たまりで渇きを癒そうとしたものの、どの水たまりも海水で飲めはしなかった。結局、助けを求めるのは諦めて船へ戻り、島を離れたところ、今までそこにあった島は海へ沈んでしまったという。実はこれが、海面へ浮上した赤えいであったとのことである。
天保12年(1841年)の江戸後期に桃山人が刊行した日本の奇談集「絵本百物語」の第3巻には「この魚その身の丈三里に余れり 背に砂たまれば落さんと海上に浮べり 其時船人島なりと思ひ舟を寄すれば水底に沈めり 然る時は浪荒くして船これがために破らる 大海に多し」とあり、現代訳語では「この魚は体長3里(約12キロメートル)を上回る。背に砂が溜まれば、砂を払い落とそうと時おり海上に現れる。人がもしこれを島と見誤って船を近づけようものなら、船は水底に沈められ荒波によって壊されてしまい、乗員も船もろとも渦に呑み込まれてしまう。この怪異は大海に多い。」となる。
信じるか信じないかはあなた次第という話ですね。
また、天明5年(1785年)成稿の林子平『三国通覧図説』にも蝦夷国(北海道)の近海に棲息し「背ノ広キコト方六七十丈(およそ200メートル前後四方)」という「鱝魚」の記述があり、その訓には「アカヱイ」と振られてある。
確認されている実際のところでは、アカエイと同じトビエイ目のエイ
であるオニイトマキエイも、大型の個体は全長5メートルから6メートル、
全幅10メートル以上におよぶことが知られている。
竹原春泉画『絵本百物語』のうち、三巻の六丁 「赤ゑいの魚」。それと知らず赤ゑいの魚の背に舟を漕ぎ着け、上陸する船乗りたち。

海坊主
海に出没し、多くは夜間に現れ、それまでは穏やかだった海面が突然盛り上がり黒い坊主頭の巨人が現れて、船を破壊するとされる。大きさは多くは数メートルから数十メートルで、かなり巨大なものもあるとされるが、比較的小さなものもいると伝えられることもある。

← のちにダイオウイカ属と判明する未知の海洋動物の、最初の標本確保の様子を伝える挿絵
1861年11月30日、カナリア諸島から出航したフランス海軍砲艦アレクタン号 (Alecton) は、海面にクジラより大きな未知の海洋動物を発見し、これに発砲した。このとき採取に成功した胴体の一部が、学会に初めてもたらされたダイオウイカ属の標本となった。
画像はハーパー・リーの著書 "Sea Monsters Unmasked(未知なる海の怪物達)"(1884年刊)に掲載されたものである。

↑ 1875年にベーリング海上にあるセン
トポール島(英語版)に打ち上げられ
た様子を描いた挿絵
原発半島で有名な下北半島の東通村尻屋崎では、フカに喰われた人間が「モウジャブネ」になるという。とwikipedia には書いていました。モウジャブネとは亡者船のことでしょう。幽霊船ですね。それより怖いのが活断層と原子力発電ではないかと思われます。
静岡県賀茂郡で語られる「ウミコゾウ」は、目の際まで毛をかぶった小僧で、釣り糸を辿って来て、にっこり笑ったという。
愛媛県北宇和郡では、夜、海が白くなって泳いでくるものを「シラミ」、または「シラミユウレン」と呼び、漁師はこれをバカと言う。しかし、バカというのが聞こえると、怒って櫓にすがり、散々な目にあわされると伝えられている。
佐渡島の「タテエボシ」は、海から立ち上る高さ20メートルもの怪物で、船目掛けて倒れて来るという。
宮城県の気仙沼大島では美女に化けて人間と泳ぎを競ったという話がある。
岩手でも同様にいわれるが、誘いに乗って泳ぐとすぐに飲み込まれてしまうという。
愛媛県宇和島市では座頭に化けて人間の女を殺したという話がある。また人を襲うという伝承が多い中、宇和島では海坊主を見ると長寿になるという伝承がある。
随筆『雨窓閑話』では桑名(現・三重県)で、月末は海坊主が出るといって船出を禁じられていたが、ある船乗りが禁を破って海に出たところ海坊主が現れ「俺は恐ろしいか」と問い、船乗りが「世を渡ることほど恐ろしいことはない」と答えると、海坊主は消えたという。これはいい話ですね。
江戸時代の古典『奇異雑談集』では「黒入道」という海坊主の記述がある。
伊勢国(現・三重県)から伊良湖岬(愛知県田原市の渥美半島先端)へ向かう船で、船頭が独り女房を断っていたところへ、善珍という者が自分の妻を強引に乗せたところ、海で大嵐に見舞われた。
船主は竜神の怒りに触れた、女が乗ったからだなどと怒り、竜神の欲しがりそうな物を海に投げ込んだものの、嵐はおさまらず、やがて黒入道の頭が現れた。
それは人間の頭の5-6倍ほどあり、目が光り、馬のような口は2尺(約60センチメートル)ほどあった。善珍の妻は意を決して海に身を投げたところ、黒入道はその妻を咥え、嵐はやんだという。このように海坊主は竜神の零落した姿であり、生贄を求めるともいう。


日立のスザンナ
FY=810 14型
そういえば、子供の頃にテレビで見た海坊主を思い出しました。映画だったのか何かの番組だったのかは思い出せませんが、静かな海の中から船より大きい「オバケのQ太郎」や「ふなっしー」のような丸い頭が出現するのです。
そばにいた親父に「海坊主は本当にいるのか」と聞いてみたら、「居るかもしれないが、まだ見たことがない。」といわれ、大きなイカならいると云ってました。
←昔々我が家にあったテレビです。
昭和35年(1960年)、日立から発売された真空管式白黒テレビ "スザンナ"です。
トップモードの横型スタイル 2スピーカー・レコーダー端子つき リモコン別
14型・超高感度・遠距離用 現金正価59.800円 月賦生価63.100円
マッコウクジラ VS ダイオウイカ
アメリカのケーブルテレビ「ディスカバリーチャンネル」で放送された動画です。
この番組では2種類の異なった動物の能力を、それぞれ機械を用いたシミュレーションで測定し、その結果に基づいて、2種が実際に闘ったらどうなるのかを推定したコンピューターグラフィックスアニメを制作して、どちらの動物が強いのかを調べるのが番組の趣旨です。
題名:マッコウクジラ対ダイオウホウズキイカ
場所:南極海
勝者:マッコウクジラ
(1987年からケーブルや衛星で、日本でも放送開始)
実際にはまだ確認されていない(2015年)捕食シーンの映像ですが、抹香鯨が超音波を放ってダイオウイカを弱らせている様子がわかりますね。
抹香鯨が放つ超音波はイルカやシャチ、その他のハクジラ系が行う反響定位(エコーロケーション)
とは出力が違うようです。
通常はメロン、またはメロン体と呼ばれる脂肪組織が頭部の中央にあって、反響定位をする際に音波を集中する働きがあるのに対して、抹香鯨の場合はそれを脳油が行っており、他の動物のメロンと比べると量も多く、化学的に異なった性質を持つと言われています。それによって強力な超音波を出すことができ、ダイオウイカを失神させたり麻痺に陥らせる事ができるのではないかという説があります。誰も見ていないので今の所は説です。
1938年、マッコウクジラとダイオウイカのバトルをロシアの動物学者ゼンコヴィッチ(B. A. Zenkovich)氏が船から目撃したという話があります。今のところ原文にたどり着いていないので本当のところはわかりませんが、ゼンコヴィッチ氏はシャチやシロナガスクジラ、特にマッコウクジラの胃の内容物をエリア別に調査していたようなので、目撃していてもおかしくはないのですが、まだ何とも言えません。
その他の目撃談
1971年4月。宮城県牡鹿郡女川町の漁船・第28金比羅丸がニュージーランド方面でマグロ漁をしていたところ、巻き上げていた延縄が突然切れ、海から大きな生物状のものが現れ、船員たちは化け物といって大騒ぎになった。
それは灰褐色で皺の多い体を持ち、目は直径15センチメートルほど、鼻はつぶれ、口は見えなかった。半身が濁った海水の中に没していたために全身は確認できなかったが、尾をひいているようにも見えたという。モリで突く準備をしていたところ、その化物は海中へと消えたという。
遠洋水産研究所の焼津分室の係員はこの目撃談を聞き、本職の漁師たちが魚やクジラなどの生物を化物と誤認することはないとしている。また目撃談では水面から現れた半身は1.5メートルほどだったといい、全身はその倍以上の大きさと推測されることから、そのような生物は聞いたこともないと話していたという。
この怪異談は、毎日新聞の同年7月17日号の新聞記事にも掲載された。
1977年4月25日午前10時40分(現地時間)、大洋漁業のトロール船「瑞洋丸」
(2460トン、乗員87名)がニュージーランドのクライストチャーチより東へ
約50km離れた海域で、正体不明の巨大な腐乱死体を引き上げた。
後にニューネッシーと呼ばれた謎の巨大生物の腐乱死体は、全長約10メート
ル、重さ1800キログラム、首の長さは1.5メートルだった。瑞洋丸が商船だった
ことと、腐敗臭が強くて持ち帰れなかったので、5枚の写真を残して海へ戻され
たのでした。
この話はよく覚えています。
当時おやじは「大発見だったかもしれないのだから、そのまま日本へ向かうか、
近くの港へ入ればよかったのだ」と言ってましたね。母船でも大方の意見がそう
だったようです。但し、南氷洋に腐乱臭は届いていなかったでしょう。
しかしてその正体は、どうやらウバザメ説が有力なようです。確定はしていま
せん。
地球に残された最後の秘境!深海。
一般的に海面下 200 m より深い海を指すが、厳密な定義は存在しない。
深海は海面面積の約 80 % を占める。
大空を飛行機が飛び、大地を自動車や鉄道が走り、海を大型タンカーが航行し、4000km上空に国際宇宙ステーションができても、深海についてはまだまだ知られてないのです。
目撃談
日本語が聞き取りにくいです。


第三日新丸 丸山シチュウジ(司厨長)撮影
この撮り方が大正解ですよね!
このホームページを見ていてくれた元第三日新丸の丸山シチュウジ(司厨長)のご子息からメールを頂き、あれやこれやと捕鯨親父の家族あるあるの話をしていたところ、1976年頃に撮ったと思われるダイオウイカの写真を見せてくれました。
ご子息の丸山さんによると
「母親いわく、手を広げてこんな大きなイカがいるんだぞ、と帰ってきてから話しても誰も信じてくれないので、ある時「これが証拠写真っっ!!」と自慢げに持ってきた写真なんだそうです(笑)
最近、ダイオウイカが騒がれるようになました
が『お父さんが撮ってきた写真がどっかにあったはず』という母親の一言で探したのがこのアルバムなんです。」

丸山シチュウジ(司厨長)が愛用していた小西六「PearlⅡ」
きっとこのカメラで撮られたのでしょう。写っている男性は、本人ではないそうです。モデルになって頂いたのでしょう。いい顔しています^^
近頃ご子息さんが実家に帰っては親父が残した宝物を掘り出しているようです。
第三日新丸は私の父も乗船しており、共同捕鯨時代まで乗っているので、親同士は知っているはずです。今頃天国で笑いながら写真の話でもしているかもしれませんね。
ご子息のホームページ
カメラ・写真
丸山正志 自分勝手なホームページ
http://qvf04120.wix.com/jp1ttr
(特別編)親父のアルバム
http://qvf04120.wix.com/jp1ttr#!grid/c1abh
2011年08月14日 おやじのアルバム 捕鯨 というブログを立ち上げた時「親父のアルバム」にするか迷ったんですよね。何を思ったか子供達にも読んで欲しいなんて事を考えてしまい、ひらがなにしてしまいました。しかし検索されても内容が伝わらないので、後で捕鯨をつけたのです。というわけでパクられた感はありません^^ 存分に親父ネタを紹介してくれると嬉しいですね。
入港式献立
赤道際 母船
しっきり
遥かに天洋丸
南氷洋にもカモメがいた