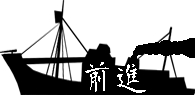お や じ の ア ル バ ム
日新丸のスリップウェイ 白鯨

おやじメモより
船艉より巻き上げられる白長須鯨 手前は口 線は腹 時には白鯨も揚げられる
お腹の線の部分がいわゆるくじらのベーコンなわけです。
そしてこの場所が日新丸のスリップウェーといって、船尾の穴から鯨を甲板まで引き上げるための通路です。
発明は1924年。ノルウェイ捕鯨において、それまでの捕鯨母船は鯨油生産のための移動工場としての機能しかなかったが、新型捕鯨母船「ランシング号(7990総トン)」には、鯨を解体作業のために船内へ収容するスリップウェイが装備された。
このことで鯨を甲板で解体できるようになり、今まで出来なかった鯨肉や骨も奇麗に解体できるようになった。
また、スリップウェーの発明で、公海上で自由に操業できる母船式捕鯨の仕組みが完成したのです。但し、クローが登場したのが1932年なので、しばらくの間は、大型鯨には手を出せなかったと思われます。もしくは相当苦労していたでしょう。
ハーマン・メルヴィル氏の白鯨に曰く「この水陸から成る地球の3分の2はナンタケットのものである。海はナンタケットのものである。皇帝が帝国を所有するように、ナンタケットは海を所有する。」("Two thirds of this terraqueous globe are the Nantucketer's. For the sea is his; he owns it, as Emperors own empires.") と傲慢な考え方がまかり通っていた1851年こそ、抹香鯨を捕まえては鯨油を採取して肉を捨てていたアメリカ式商業捕鯨が真っ盛りだったのだ。
因みに抹香鯨は歯クジラですが、上あごに歯がないので、エイハブ船長の足を食いちぎるほどの力はありません。捕食したダイオウイカも、ほぼそのまま胃袋から出てきます。どうしても悪魔にしたかったのでしょう^^
そして、小説白鯨の捕鯨船ピークォド号は、ついに日本近海で白い抹香鯨を発見し、戦いに挑むが沈没することとなる。
2006年8月、オーストラリアパース沿岸で撮影さ��れたミナミセミクジラのアルビノ(動物学においては、メラニンの生合成に係わる遺伝情報の欠損により 先天的にメラニンが欠乏する遺伝子疾患、ならびにその症状を伴う個体のことを指す。)の生後2ヶ月ぐらいの赤ちゃんだと思われる白鯨。
2007年にもザトウ鯨のアルピノが目撃されている。
2011年9月には、オーストラリアのグレートバリアリーフでザトウ鯨のアルミノを発見。
2年後の1853年。今度は現実ですが、アメリカ合衆国海軍東インド艦隊の黒船が久里浜沖に姿を見せるのである(黒船来航)。
さて、小説白鯨の白い抹香鯨がアルビノ(albino)かどうかという議論もあるようですが、私としては小説なんだからいいんじゃないの?と思う。
それよりも、当時南氷洋捕鯨に携わっていた人であれば、一度や二度は白鯨を見ていても不思議ではなさそうですね。
白鯨は本当にいるのか

白鯨といえば
1851年に発表されたハーマン・メルヴィルの長編小説『白鯨』が有名ですよね。映画化されてますし、Youtubeにもあります。
物語は19世紀のアメリカ。マサチューセッツ州ケープ・コッドの南30マイルに位置するナンタケット (Nantucket)の捕鯨基地にはじまる。
この小説でいう白鯨は抹香鯨です。なんと悪魔のような悪役にされているではないか。
登場人物の船長であるエイハブは、白い抹香鯨に片足を食いちぎられており、鯨骨製の義足を装着して登場する。船長エイハブの白い抹香鯨に対する恨みは狂気に達し、乗組員にも感染する。そして白鯨に報復を誓い合った捕鯨船ピークォド号(捕鯨帆船エセックス号)は出港した。
命中!
命中!
日新丸 船尾
スリップウェイ 抹香鯨
解体風景 秋田組と岩手組
マルハ木曜�アワー
くじらのベーコン