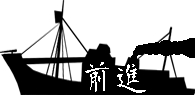お や じ の ア ル バ ム

迂回 大氷山
おやじメモ
凡長四里の大氷山に道をふさがれし
一時バックしてから新漁場に向かったのも事実だ
四里といえば、4km×4=16kmです。
そんなに大きい氷山があるのか・・・・・・あった。

【ワシントン共同】南極の氷河に亀裂が入り、巨大な氷山ができつつある様子を、米航空宇宙局(NASA)の地球観測衛星「テラ」に搭載された観測機器の一つで、日本の経済産業省が開発した光学センサー「ASTER」がとらえた。
写真は昨年(2011)11月に撮影。南極西部のパインアイランド氷河に幅80メートル、深さ60メートルほどの亀裂が約30キロにわたって生じた。亀裂はさらに伸び、近く東京23区の面積の約1・4倍に相当する約900平方キロの巨大氷山となって分離する見通しだという。
16kmどころの話じゃありませんね。
2012年2月7日、この亀裂は順調に広がっており、もうすぐ大氷山が誕生する。
(2012年02月18日)


氷山監視組織
氷山は、1912年(大正元年)4月14日の夜に氷山に衝突して翌日沈んだオリンピック(タイタニック)海難事故を教訓にして、1914年(大正3年)にInternational Ice Patrol が設立され、北大西洋の氷山を監視しています。南極の氷山はアメリカの National Ice Center が監視しています。
残念ながら古い記録は発見できませんでしたが、その南極で2000年にロス棚氷から分離した氷山B15は、最初面積が1万1000㎢あり、記録されたものの中で最大でありました。
2002年11月には2つに分裂したものの、2004年12月の時点でも、最大のもの(B15A)は面積が3000㎢あり、依然世界最大であったといいます。
今回のパイン島氷河で誕生する大氷山が900㎢ですから、B15Aは桁が違いますね。
20世紀以降の氷河の後退に伴って大規模な氷山の誕生(棚氷や氷河の崩落)が増加傾向にあるとされており、地球温暖化の影響ではないかと考えられています。
そして3月11日。東日本で甚大な被害をもたらした津波は18時間後、約13,000kmの距離を進んで南極大陸に到達し、氷河を崩壊させていました。津波の高さは30cmほどでしたが、到達したのは単なる波ではなくM9.0が生み出した津波の底力なのです。
分離した氷山は合わせて約120平方km。サルツバーガー氷棚を離れてロス海に流れ出た最も大きな氷山は、長さが約11km、幅が約6.5kmもあった。
NASA | Tohoku Tsunami Creates Antarctic Icebergs
NASAによると
2011年に観測されたパイン島氷河は2013年7月10日、ついに南極大陸から分離したようです。
サイズは12マイル(1国際マイル=1609.344m ×12=
19.312km)×21マイル(33.796km )=650km²。

興味がある方は、JAXA宇宙航空研究開発機構の
パイン島氷河の分離の様子 2013年11月1日~2014年3月
11日の CAI RGB画像をご覧いただけます。
というわけで、氷山というものは四里(16km)どころの話ではないようです。


氷山の大きさ
青空
船のような氷山 船の大きさくらべ 正和丸