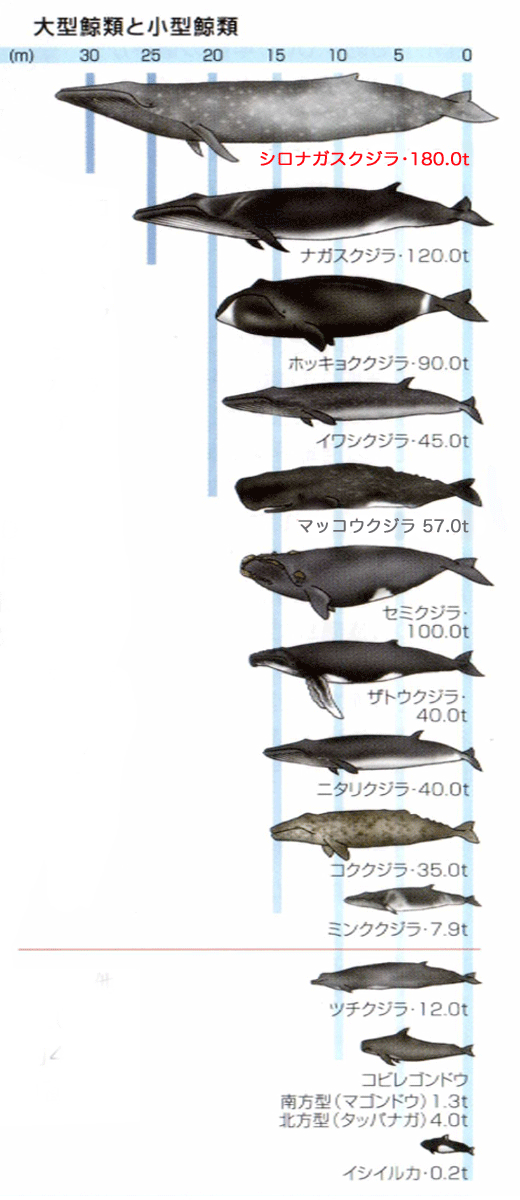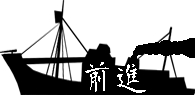お や じ の ア ル バ ム
白長須鯨 シロナガスクジラ

でかいですね~!
おやじの書き込みによると
最長104尺 17間余 昭和25年頃一頭当300万円(白長須鯨)
甲板部の解剖1頭20分
昭和28年12月写
1尺は明治時代に約303mmと定義されているので、104尺は31521mm。31m52.1cmですね。
たった20分で解体しちゃうんですね。
そのへんの事を書いているサイトが有ったので紹介します。
1998年、
このページの最後の方に「鯨の解体を見るのは、初めてだったが、気持ち悪いどころか、肉を無駄にしないよう、さばく技術が素晴らしい。鯨は捨てるところがないといった利用価値が育んだものかもしれないが、彼らの包丁さばきに、心から感動する。彼らの仕事を見ていくうちに、生きものを殺して食べるという大事なファクターがここにあることを確信する。」とあります。
なるほどそうかもしれませんね。できれば皆さんにもこのサイトのあっちこっちを見て欲しいと思います。
さて、宗教や哲学的な話はもうちょいとおいといて、白長須鯨について話を進めましょう。
wikipedia によると、シロナガスクジラ(白長須鯨、Balaenoptera musculus)は、鯨偶蹄目ナガスクジラ科ナガスクジラ属に属するクジラの1種であり、な~~~んと、かつて地球上に存在した動物を含め、あらゆる既知の動物の中で最大の種であり、記録では体長34メートルのものまで確認されているそうです。
でかっ!
主にプランクトン、いわし等の小魚を食べるが、時にはアジなどの中型魚も食べている。
シロナガスクジラは巨大で高速なことから捕獲が困難で、古くは捕鯨の対象とはならず、元々の個体数は30万頭いたと推定されている。 近年、個体数は年々増加し続けているものの、総計で1万頭前後と非常に少なく、絶滅危惧種に指定されている。
日本捕鯨教会のパンフレットで他の鯨と大きさを比較してみましょう。
東北新幹線E5系約42t
ダントツでデカイですね^^
時速320kmで走る東北新幹線のE5系先頭車でも26.5mです(中間車両は25m)。
因みに牛一頭がおよそ600kgだとすると、単純に180,000/600 = 300頭分です。
1つの命も300の命も、命の重みは同じでしょう
けど、確かに効率いいんですよねぇ~。
まず、家畜のように餌代も掛からなければ育てる手間も掛かりません。広大な土地も施設もいらないんです。
船の建造にはお金が掛かりますが、島国ニッポンにとっては自給率を上げる為にも捕鯨技術は継がれるべきものだと思うんですよね。
今は調査捕鯨ですが、獲りすぎないように管理をちゃんとすれば、充分やれると思うんですけどねぇ~。
この地球上には戦後の日本のように食べられない人が沢山居るのですから、鯨肉を使ってもいいような気がしますが、どうでしょう?
解決しがたい問題があるとすれば、地球の海が日本のモノではないという事でしょうか。
アメリカ式捕鯨
アメリカではおよそ17世紀の中頃から北米大陸東岸で捕鯨が始まった。目的はマッコウクジラから採れる良質の鯨油である。よって鯨油さえ採取できれば、肉等は殆ど捨ててしまうという商業捕鯨であった。
18世紀半ばに産業革命が起こると、アメリカ国内の工場やオフィスは夜遅くまで稼動するようになり、その潤滑油やランプの灯火として、主にマッコウクジラの鯨油が使用されていた。
それでも当初は沿岸捕鯨だったが、ついに資源の枯渇から18世紀には大型の帆走捕鯨船を本船としたアメリカ式捕鯨へと移行する。
身勝手な拡大
操業海域も太西洋が中心となり、また新たに資源を求めて太平洋全域へ活動を拡大していった。北ではベーリング海峡を抜けて北極海にまで進出してホッキョククジラを捕獲し、南ではオーストラリア大陸周辺や南大西洋のサウス・ジョージア諸島まで活動した。
19世紀に入ると日本周辺にも1820年代に到達し、極めて資源豊富な漁場であるとして多数の捕鯨船が集まった。
嘉永6年(1853年)の黒船来航も捕鯨基地を確保する事が主な目的だった。
捕鯨船の大型化
操業海域の拡大にあわせて捕鯨船は排水量300トン以上に大型化し、大型のカッターでクジラを追い込み、銛で捕獲し、船上に据えた炉と釜で皮などを煮て採油し、採油した油は船内で制作した樽に保存し、薪水を出先で補給しながら(このような事情が日米和親条約締結へのアメリカの最初の動機であった)、母港帰港まで最長4年以上の航海を続けるようになった。
捕獲用器具としては手投げ式の銛に加え、1840年代に炸薬付の銛を発射するボムランス銃 (Bomb Lance Gun、ボンブランスとも)と呼ばれる捕鯨銃が開発された。捕獲対象種にはコククジラやセミクジラ、ザトウクジラも加わり、鯨油と鯨ひげの需要に応じて捕獲対象種の重点が決定された。
19世紀中頃には最盛期を迎え、イギリス船などもあわせ太平洋で操業する捕鯨船の数は500~700隻に達し、アメリカ船だけでマッコウクジラとセミクジラ各5千頭、イギリス船などを合わせるとマッコウクジラ7千~1万頭を1年に捕獲していた。南大西洋ではアザラシ猟も副業として行い、アフリカから奴隷を運んではアザラシ猟に従事させ、その間に捕鯨をしていた。捕鯨船の母港となったナンタケットやニュー・ベッドフォードは大いに繁栄した。メルヴィルの『白鯨』は、この時期の捕鯨を描いたものである。
鯨の激減と油田
太平洋においても大西洋の場合と同様に資源の減少が起きた。カリフォルニア州沿岸のコククジラは激減し、マッコウクジラやセミクジラも大きく減少した。アメリカ式捕鯨による西太平洋でのセミクジラ資源減少は、日本の古式捕鯨の衰退にも影響したとの見方がある。
こうした資源枯渇に加え、ペンシルベニア州での油田発見による灯火用の鯨油需要減少や、北米西部でのゴールドラッシュに捕鯨労働者の多くが転向したことにより、アメリカにおける捕鯨は衰退に向かった。長い間機械文明を支えていたのは鯨油でした。はて、アメリカは鯨に感謝していただろうか。
おやじもよく言ってました。鯨は捨てるところがないのだと。
鯨の活用図
<イラスト提供:(財)日本鯨類研究所>
参考資料:wikipedia 捕鯨
白長須鯨 2
くじらの赤肉
くじらのベーコン
命中!
スリップウエイ
抹香鯨
竹田船団長
カメラ